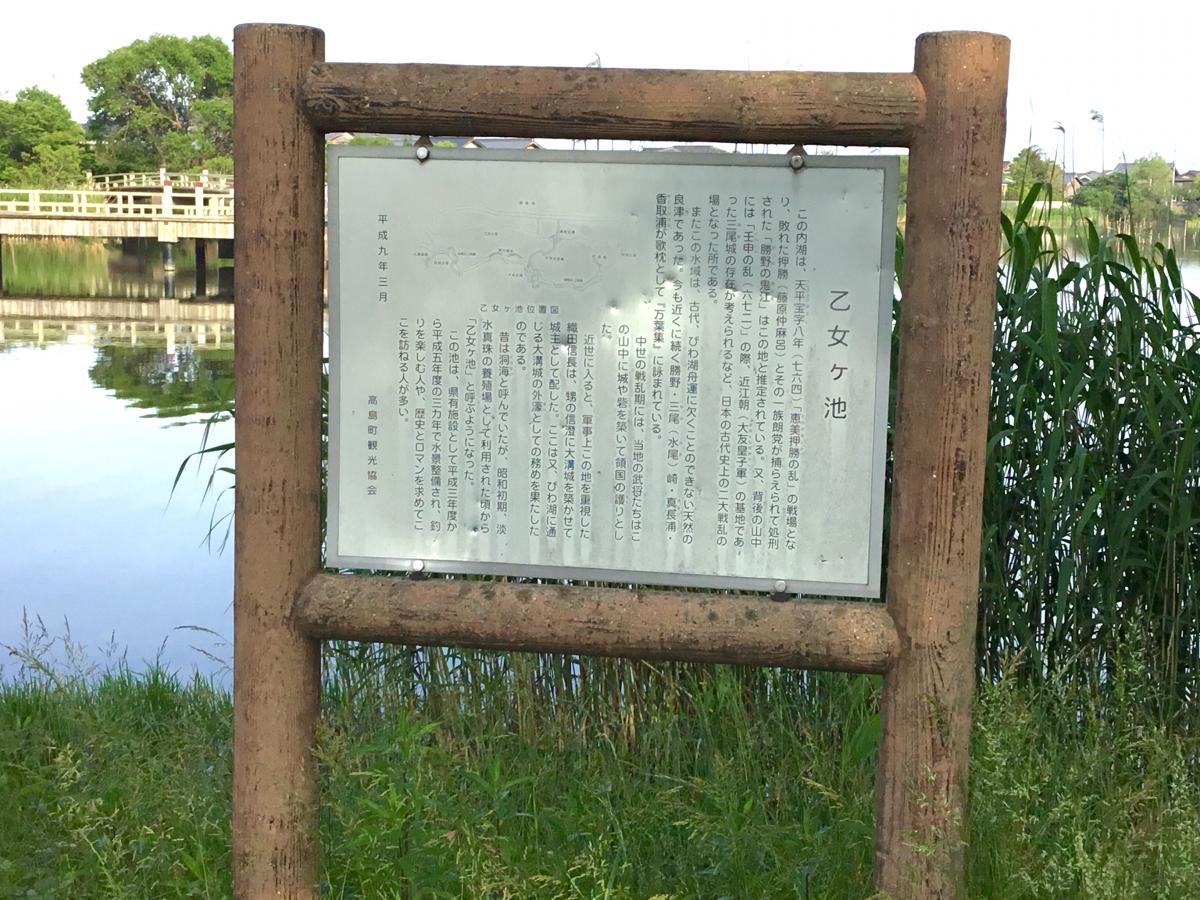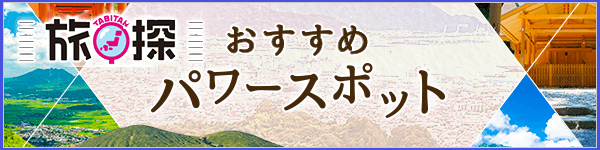藤原仲麻呂
藤原仲麻呂は、第45代天皇「光明皇后」(こうみょうこうごう)の甥っ子で、左大臣を務めた「藤原武智麻呂」(ふじわらのむちまろ)の次男という、エリート貴族の家に生まれました。
藤原家は、光明皇后を後ろ盾として政権を担っていましたが、737年(天平9年)天然痘が流行し、父である藤原武智麻呂が死去。
これによって、次の政権を担ったのが左大臣であった「橘諸兄」(たちばなのもろえ)でした。
橘家の台頭によって、藤原家の勢力はいったん衰えたように思われましたが、橘諸兄の政権下になっても、光明皇后を後ろ盾に藤原仲麻呂は順調に出世します。743年(天平15年)に「公爵」(こうしゃく:貴族の称号の第一位)になり、746年(天平18年)には、人事権を握る「式部省」(しきぶしょう)にまで上り詰めます。しかし、策略家だった藤原仲麻呂は、大幅な人事異動を行なうなどして、橘諸兄の勢力を徐々に削いでいったのです。
その後、749年(天平勝宝元年)に「聖武天皇」(しょうむてんのう)が譲位し、娘の「孝謙天皇」(こうけんてんのう)が即位すると、藤原仲麻呂は「大納言」に昇進。さらに、「紫微中台」(しびちゅうだい:政治・軍事機関)と「中衛大将」(ちゅうえのだいしょう:主君を護衛する軍)の長官もかねていたことにより、事実上、光明皇后と藤原仲麻呂が政権と軍権を掌握することとなりました。