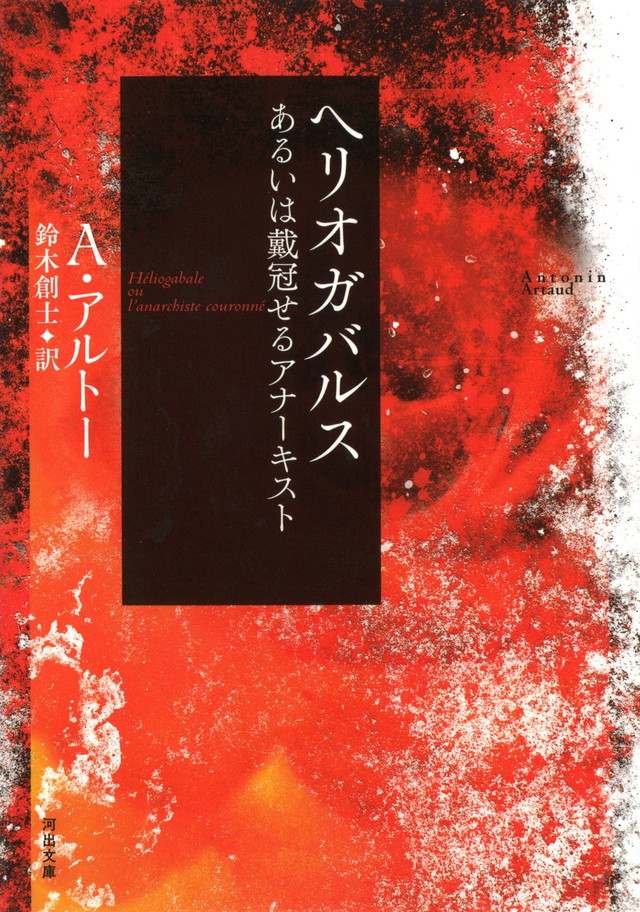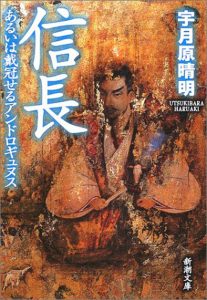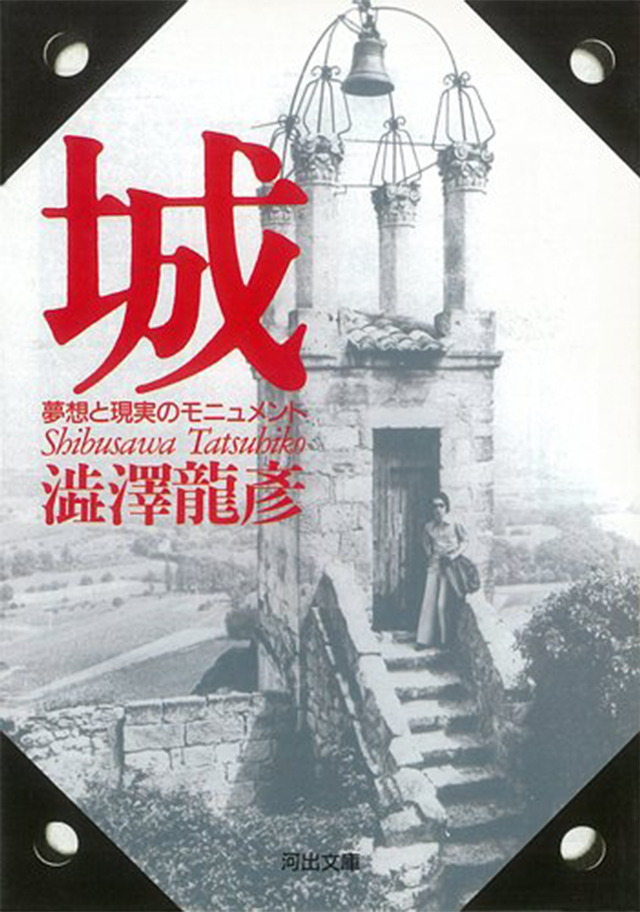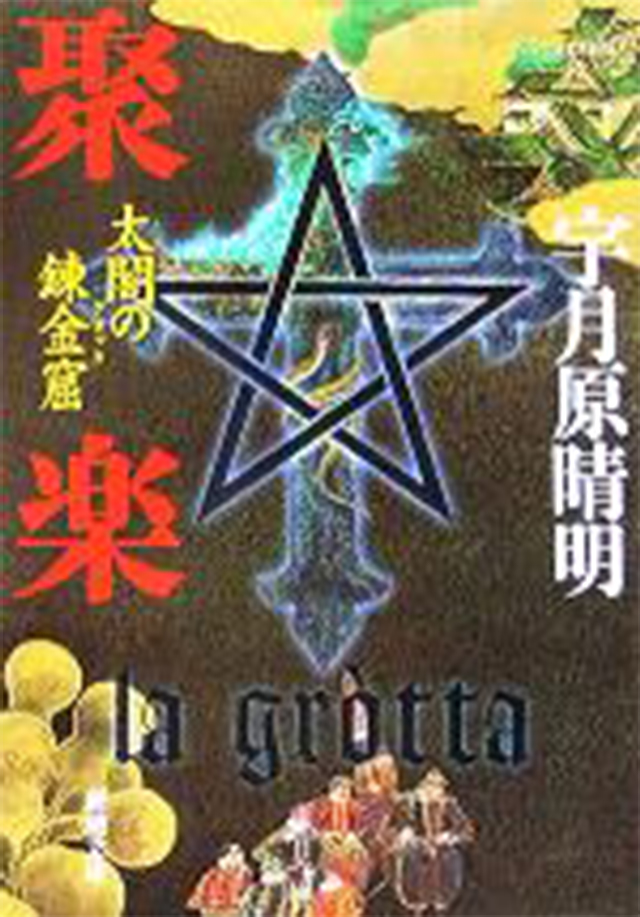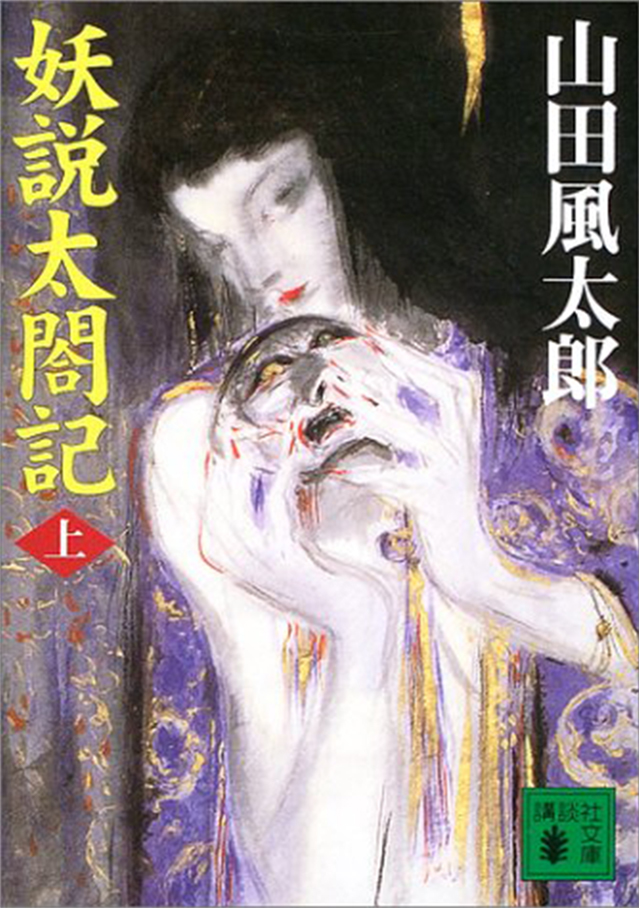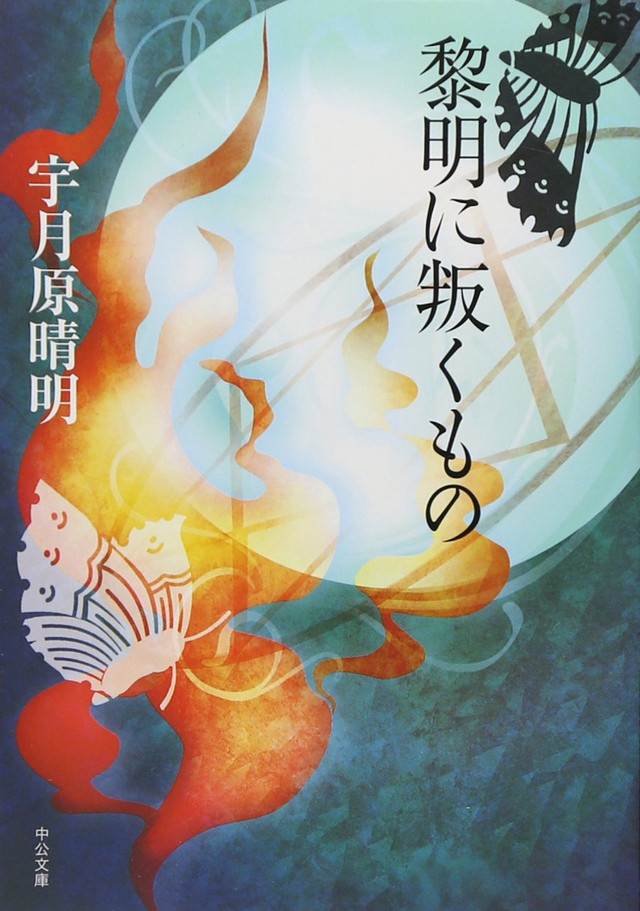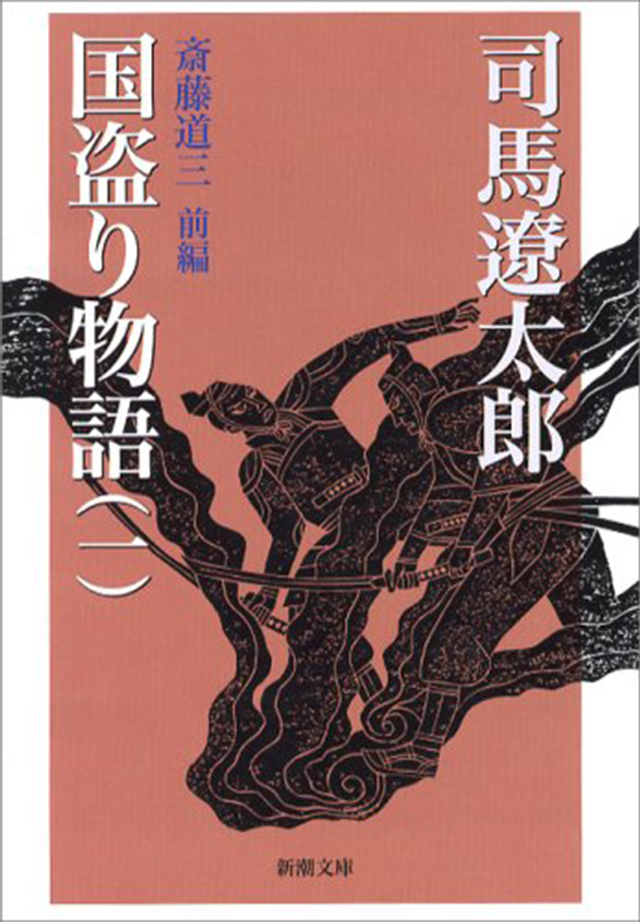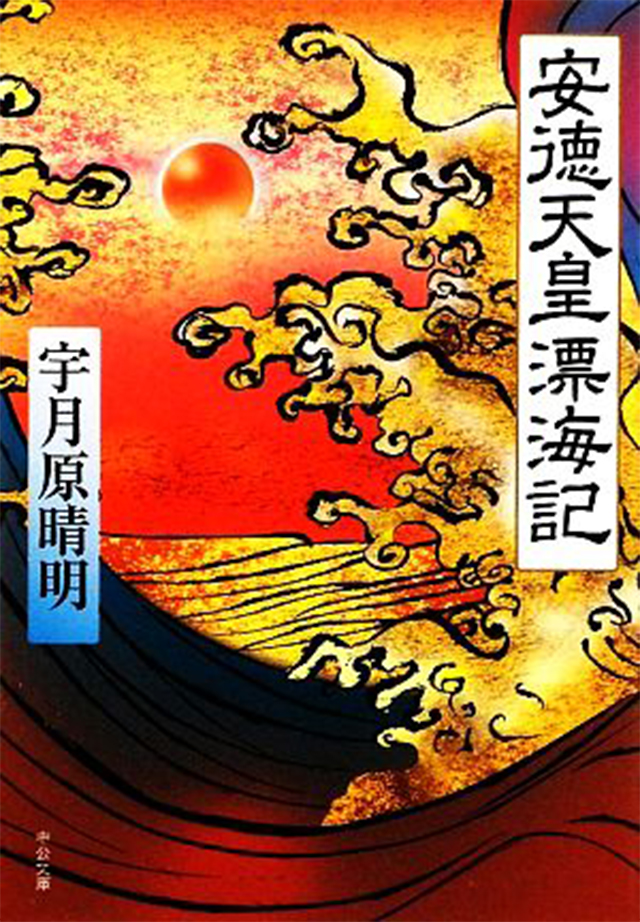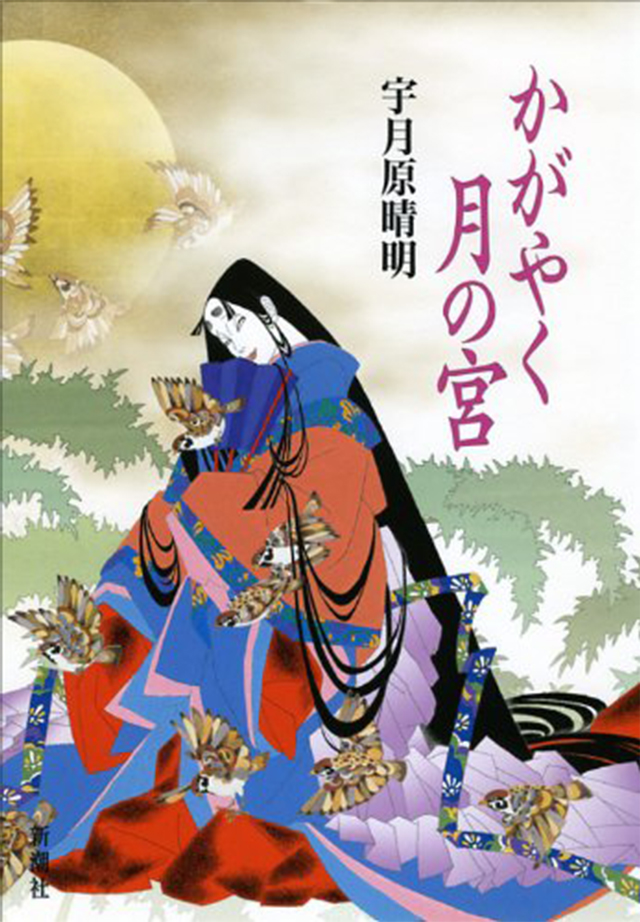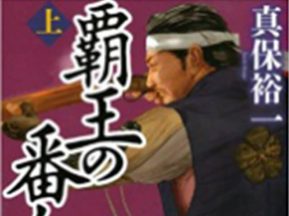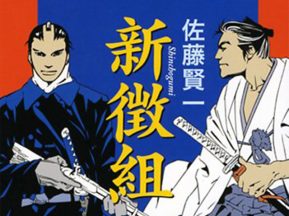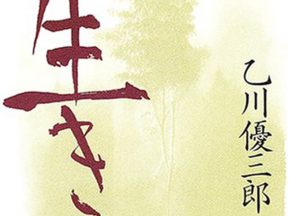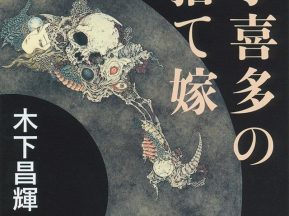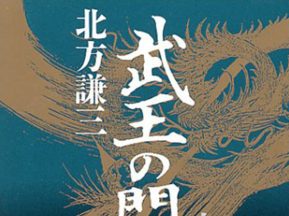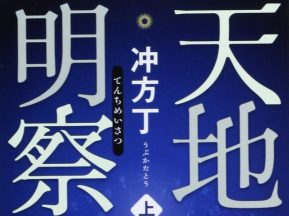『聚楽 太閤の錬金窟』では乱行を繰り返していたとされる豊臣秀次の史実をふまえ、豊臣秀次の命でさらわれた若い娘を使った秘術が夜ごと聚楽第の地下で行なわれます。
百年戦争期のフランスの軍人ジル・ド・レ(男装者ジャンヌ・ダルクの同士。ジャンヌ・ダルク処刑後に居城で黒魔術にのめり込む。誘拐した子供の大量殺人者を主人公とするシャルル・ペローの童話『青髭』のモデル)の物語が豊臣秀次に重ね合わされます。
聚楽第では、同時代に実在したユダヤ神秘主義者でイエズス会を破門されたギヨーム・ポステルが豊臣秀次に取り入り錬金術を行ない、人造人間(ホムンクルス)の創造に挑みます。
そこに、織田信長を信奉する徳川家康の支え、ギヨーム・ポステルを追うイエズス会の異端審問組織など思惑がからみます。
この幻想的な物語の背景には、豊臣秀吉とお市の方(織田信長の妹で浅井長政と政略結婚)との因縁があります。
浅井長政には正室や側室との間に嫡男・万福丸と万寿丸の他に円寿丸などがいたとされます。継室・お市の方との間には3姉妹(茶々・初・江)が生まれています。
織田信長に敗れた浅井長政が自害した小谷城の戦いの際、羽柴(豊臣)秀吉は織田信長の命で万福丸を殺害。万寿丸は僧侶になったとされています。
『聚楽 太閤の錬金窟』ではその円寿丸が実在し、小谷城の戦い後に行方不明になったとされ、その生母はお市の方とされます。そして茶々(淀の方)と豊臣秀次は似ているとされます。
豊臣秀吉は豊臣秀次がどんなに乱行をしようともとことん甘く許します。同作ではお市の方を愛していたとされる豊臣秀吉像が導入されています。
さらに豊臣秀吉に仕えた御伽衆・曽呂利新左衛門(初代)を豊臣秀次の味方とします。前半生が不明の彼のルーツを浅井久政(浅井長政の父)の娘・京極マリアの遺臣とし、豊臣家と浅井家の争いを描きました。
そんな『聚楽 太閤の錬金窟』では、『信長 あるいは戴冠せるアンドロギュヌス』で登場した両性具有の織田信長が蘇ります。
「猿!」
疳高い、しかし鋭く大きな、まぎれもなくあの声。あの、全身全霊を恍惚のうちに支配する主人の呼び声だ。見間違いようもない市姫の唇から発せられる、その兄の声!
(中略)
市姫にして信長、妹にして兄、母にして父なるものが、太陽にして月のような鋭利にして甘美な瞳で、秀吉を見下ろしている。
(中略)
少女の肩からのびる少年の染みひとつないすらりとした右腕が動いた。握りしめられた銀と金の剣が、ゆっくりふり上げられる。
『聚楽 太閤の錬金窟』