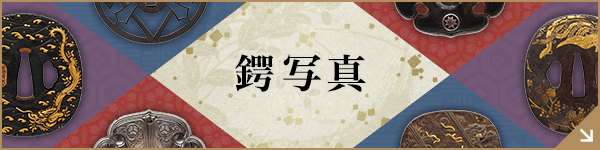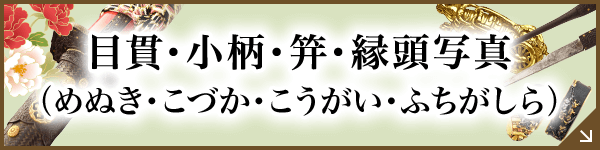刀装具は、服装と同じように時代の流行や感性が如実に表れることから、制作された時代によってデザインが異なります。そのため、刀装具の時代を判別したいと考えるなら、その時代に流行したモチーフや装飾の仕方をチェックしておく必要があるのです。
なお、現存する刀装具は室町時代中期の作が最古とされており、古い物ほど歴史的価値が高く、貴重とされています。ここでは、刀装具の時代ごとの大まかな特徴を見ていきましょう。
- 室町時代
-

応仁鍔
室町時代の刀装具は、はじめ「太刀拵」に用いられる物が主流で、鉄製で実戦向けの武骨な刀装具が制作されていました。
甲冑師や刀工が鍔の制作も手掛けており、甲冑師が作った物を「甲冑師鍔」、刀工が作った物を「刀匠鍔」と呼びます。
室町時代中期になると金工師の元祖とされる後藤祐乗により、華やかで装飾的な刀装具が誕生。金工技術が一気に向上し、室町時代後期には「平安城式真鍮象嵌鍔」(へいあんじょうしきしんちゅうぞうがんつば)や「応仁鍔」、「鎌倉鍔」などの、透かしや象嵌などで装飾された刀装具が次々に生まれました。
- 戦国時代~安土桃山時代
-

尾張透鍔
戦国時代以降の刀装具は、片手打ちができる「打刀拵」が主流となっていきます。
また、金工師やその流派が増えたことで技術が向上。戦国時代は「茶の湯」に代表される「侘び寂び」の文化が流行したことから、刀装具のデザインにも侘び寂びが取り入れられました。
その他、甲冑(鎧兜)と同様に、刀装具のデザインには勝利や信仰など、何かしらに意味を持たせた物が多いのが特徴。動植物や海産物、架空の生き物や神事、道具などがモチーフの主流で、力強くデフォルメされた表現が多用されました。
しかし、「豊臣秀吉」による「刀狩り」が行われたことで、農民や僧兵の所持していた刀装具のほとんどはなくなり、後世に残されたのは商人や武士階級が所有した高品質な物ばかり。
すなわち、安土桃山時代以前の現存する刀装具は極めて高い技術とデザイン性を持った物が多く、刀装具の価値が古い物ほど高く評価されることにつながります。
この時代、鉄鍔では「尾張鍔」や「金山鍔」など、尾張国(現在の愛知県西部)を中心にその土地特有のデザインが流行した他、金工師の祖を輩出した後藤家の上三代・後藤祐乗、「後藤宗乗」(ごとうそうじょう)、「後藤乗真」(ごとうじょうしん)が活躍しました。
- 江戸時代
-
江戸時代の刀装具は、平和な時代となったことで一層華やかとなり、様々な色金、彫金技法を駆使して装飾的な刀装具が数多く制作されるようになります。
江戸初期から江戸中期にかけては、武士の刀装具に細かい規定が設けられたことで、刀装具の制作に効率が求められるようになり、規格に則った品が大量に制作されました。
デザインは写実的、絵画的な表現が多くみられるようになり、モチーフも変化。人物や風景、情景などが選ばれるようになりました。
江戸時代を代表する町彫の金工師に、「横谷宗珉」(よこやそうみん)や「柳川派」(やながわは)、「石黒派」、「大森派」などが存在します。
- 幕末~明治時代
-
幕末から明治時代にかけての刀装具は、江戸時代を通して醸成された優れた技巧を駆使して制作された物が数多く現存しています。
開国により海外の影響も受けた華やかな作品が制作され、技術的にも大成。実用としての刀装具の制作は一時下火となりましたが、「帝室技芸員」として技術者が国に保護されたことで再興し、美術品としての価値を取り戻しました。
「加納夏雄」(かのうなつお)や「正阿弥勝義」(しょうあみかつよし)、「後藤一乗」(ごとういちじょう)などが高名な金工師として挙げられます。
- 現代
- 現代の金工師は、主に居合刀に用いる刀装具の制作を請け負っている他、修復なども手掛けていることがほとんど。また、観賞用の華やかな刀装具も制作しています。過去の高名な作品を模して制作した物も多いため、贋作には注意が必要です。