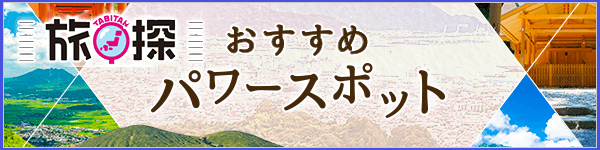松山城の築城が開始されたのは、1602年(慶長7年)。創設者は加藤嘉明です。
加藤嘉明は、「加藤清正」(かとうきよまさ)や「福島正則」(ふくしままさのり)などと共に、幼少期から「豊臣秀吉」に仕えました。1583年(天正11年)「賤ヶ岳の戦い」(しずがたけのたたかい)では、「賤ヶ岳七本槍」のひとりと呼ばれるほど活躍し、九州征伐、小田原征伐、朝鮮出兵でも武功を挙げます。その冷静さと豪胆さをかね備えた戦いぶりから、付いた異名は「沈勇の士」。
そして、1600年(慶長5年)の「関ヶ原の戦い」では、「徳川家康」に従軍し、戦功として20万石を獲得すると共に、勝山の土地に築城を許可され、松山城と命名したのです。
築城は20年以上に及んだものの、加藤嘉明は完成前に会津へ転封となり、1627年(寛永4年)「蒲生忠知」(がもうただちか:氏郷の孫)の代に完成しました。
しかし、蒲生家は世継がなく断絶。その後は、1635年(寛永12年)に、久松松平家の「松平定行」(まつだいらさだゆき:叔父は徳川家康)が入封します。
1784年(天明4年)に落雷があり、天守が焼失。現在の天守は1854年(安政元年)に松平家12代藩主「松平勝善」が再興しました。三重三階地下一階の層塔型(そうとうがた)。「連立式天守」と言い、複雑で防備が厳重な形式。再興ながら、江戸時代以前に建設された天守を有する城として、「現存12天守」のひとつにもなっています。
また、天守の鬼瓦紋は、すべて徳川家ゆかりの「丸に三つ葉葵」となっているのが特徴です。
注目すべきは、天守を含め、一ノ門、二ノ門など21棟が重要文化財に指定されていること。国指定史跡であり、「日本100名城」、「美しい日本の歴史的風土100選」にも選ばれています。
天守内には、松山城ゆかりの日本刀や甲冑(鎧兜)、書画などが悠然と展示されています。
特に、初代藩主・加藤嘉明所用と伝えられる甲冑(鎧兜)は必見。「角頭巾形鳥尾飾兜・漆塗佛胴六間草摺素懸縅鎧」(すみずきんなりとりおかざりかぶと・うるしぬりぶつどうろっけんくさずりすがけおどしよろい)は、兜の左右に付いている、大きな鳥の羽飾りがユニーク。
久松松平家初代藩主・定行所用と伝わる「鉄赤漆塗連山桶側胴具足」(てつあかうるしぬりれんざんおけがわどうぐそく)や、龍の前立てが付いた4代藩主・定直所用の「鉄切付五枚胴紺絲縅具足」(てつきりつけごまいどうこんいとおどしぐそく)など、見ごたえ充分です。体験コーナーでは、レプリカの甲冑(鎧兜)を試着することができます。
また、「刀/銘 重要無形文化財 龍泉髙橋貞次彫同作(花押)」など、わが国最初の人間国宝(重要無形文化財)となった、愛媛県出身の「髙橋貞次」(たかはしさだつぐ)の作品を複数展示。その他、実際に日本刀を持って、重さを体感できる楽しいコーナーなども設けられています。
 鑑定区分
鑑定区分
 時代
時代
 制作国
制作国
 刀工
刀工