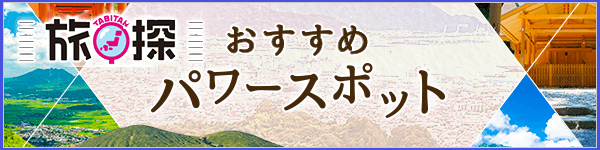「小田原城」は、1417年(応永24年)頃に、相模国足柄下郡(さがみのくにあしがらしもぐん:現在の神奈川県西部)の領主「大森頼春」(おおもりよりはる)によって築城されました。
その後、1495年(明応4年)に北条氏の祖「伊勢宗瑞」(いせそうずい:のちの北条早雲[ほうじょうそううん])が、小田原城を奪取。伊勢氏は、小田原城を拠点に据えて、5代(およそ100年)に亘り関東地方で勢力を拡大していきます。
小田原城を関東攻略の要衝とするにあたり、整備拡張を繰り返し、「豊臣秀吉」の侵攻を防ぐために築いた総構は約9km。史上最大の規模となった小田原城ですが、1590年(天正18年)に、豊臣秀吉による天下統一最後の侵攻戦「小田原征伐」によって北条氏は豊臣秀吉に敗れ、滅亡に至ります。
小田原城の城主は、「徳川家康」の重臣「大久保忠世」(おおくぼただよ)に引き継がれますが、大久保忠世の嫡男「忠隣」(ただちか)の代で大久保氏は失脚。1619年(元和5年)には、「阿部正次」(あべまさつぐ:徳川家家臣)が入城するも、約4年で武蔵国岩槻藩(むさしのくにいわつきはん:現在の埼玉県さいたま市)に転封されます。
その後も徳川家家臣の稲葉氏、大久保氏に引き継がれていきますが、1633年(寛永10年)と1703年(元禄16年)に起きた大地震により、天守や櫓が倒壊。さらに、1707年(宝永4年)には、富士山が噴火するなど、度重なる大災害によって藩の財政が圧迫されていきました。
修繕が困難なほど財政難に陥った結果、維持費を捻出することができなくなり、廃城令が出される前の1870年(明治3年)、小田原最後の藩主「大久保忠良」(おおくぼただよし)は、廃城届を提出。
こうして、史上最大規模を誇った関東の小田原城は、天守閣を含めたほとんどの建造物が解体されました。その後、1901年(明治34年)に、城跡内に「小田原御用邸」(おだわらごようてい:皇族の別荘)を設置。
また、1909年(明治42年)には、唯一取り壊されなかった二の丸「平櫓」の修築工事が行なわれますが、御用邸と平櫓は、1923年(大正12年)に起きた関東大震災により大破・倒壊し、また、このときに残っていた石垣も大部分が崩壊しています。
昭和に入ると、地元市民たちの熱い要望と小田原市の「市制20周年記念事業」などの後押しで小田原城跡内に少しずつ、櫓や天守など、当時の建造物が復元されていきました。
そして、2006年(平成18年)に小田原城は、「日本100名城」に選定。小田原城跡は現在、城址公園として市民から親しまれる憩いの場になっています。
また、近年進められている史跡発掘調査によって、戦国時代初期から近代までの遺構が多数検出されており、当時の町屋がどのような姿であったのかが少しずつ明らかになってきました。
豊臣秀吉歴史を動かした有名な戦国武将や戦い(合戦)をご紹介!
豊臣秀吉と刀豊臣秀吉のエピソードや、関連のある刀剣・日本刀をご紹介します。
徳川家康歴史を動かした有名な戦国武将や戦い(合戦)をご紹介!
徳川家康と刀徳川家康のエピソードや、関連のある刀剣・日本刀をご紹介します。
北条早雲歴史を動かした有名な戦国武将や戦い(合戦)をご紹介!
小田原の役武将達が戦った全国各地の古戦場をご紹介!
3層4階の複合式天守閣である小田原城内には、多数の刀剣や甲冑が常設展示されています。
太刀「相州小田原住義助」(そうしゅうおだわらじゅうぎすけ)は、小田原ゆかりの刀工「義助」(ぎすけ/よしすけ)が作刀した1振。義助は、駿河国嶋田(するがのくにしまだ:現在の静岡県島田市)で活動していた刀工で、小田原北条氏から招かれて小田原へ移り住みました。
義助の作で「小田原住」と銘を切ってある作品は珍しいため、本刀は貴重な1振と言えます。
「縦矧桶側二枚胴具足」(たてびきおけがわにまいどうぐそく)は、北条早雲の末子「幻庵」(げんあん)の次男「氏信」(うじのぶ)が所用していたと言われる甲冑です。補修された部分もありますが、大部分は当時のままの姿をしています。
天守から東側、城址公園の中央付近に位置する城門「常盤木門」(ときわぎもん)のなかにある「SAMURAI館」は、天守の「平成の大改修」に伴い、2016年(平成28年)に新たな展示スペースとして作られた展示室です。
武士の精神性・武具の美術性に焦点を当てた展示スペースとなっており、刀剣と甲冑の展示の他、プロジェクションマッピングを用いた甲冑を「魅せる」演出は、見た人を感動させる躍動感があります。
SAMURAI館に展示されている「錆地塗八枚張兜」(さびじぬりはちまいはりかぶと)は、甲冑師「明珍」(みょうちん)が制作した兜です。
明珍は、近世甲冑師のなかでも最も有名な一派で、分派が多く存在し、北は青森県弘前市から、南は広島県まで広がりを見せていました。なお、分派のひとつである姫路明珍派の子孫は現代でも、刀鍛冶として活躍しています。
 鑑定区分
鑑定区分
 時代
時代
 制作国
制作国
 刀工
刀工