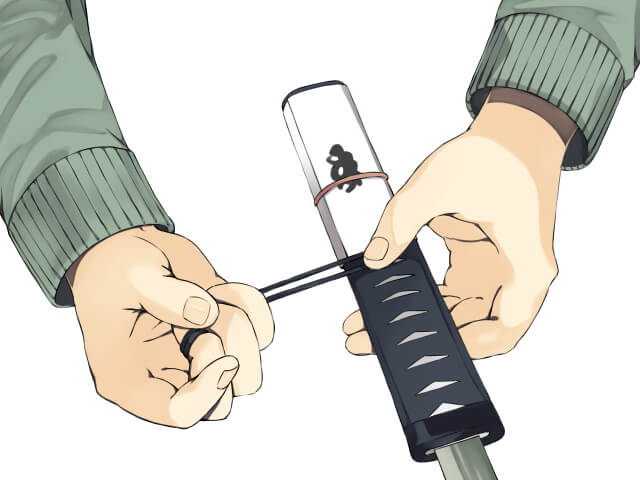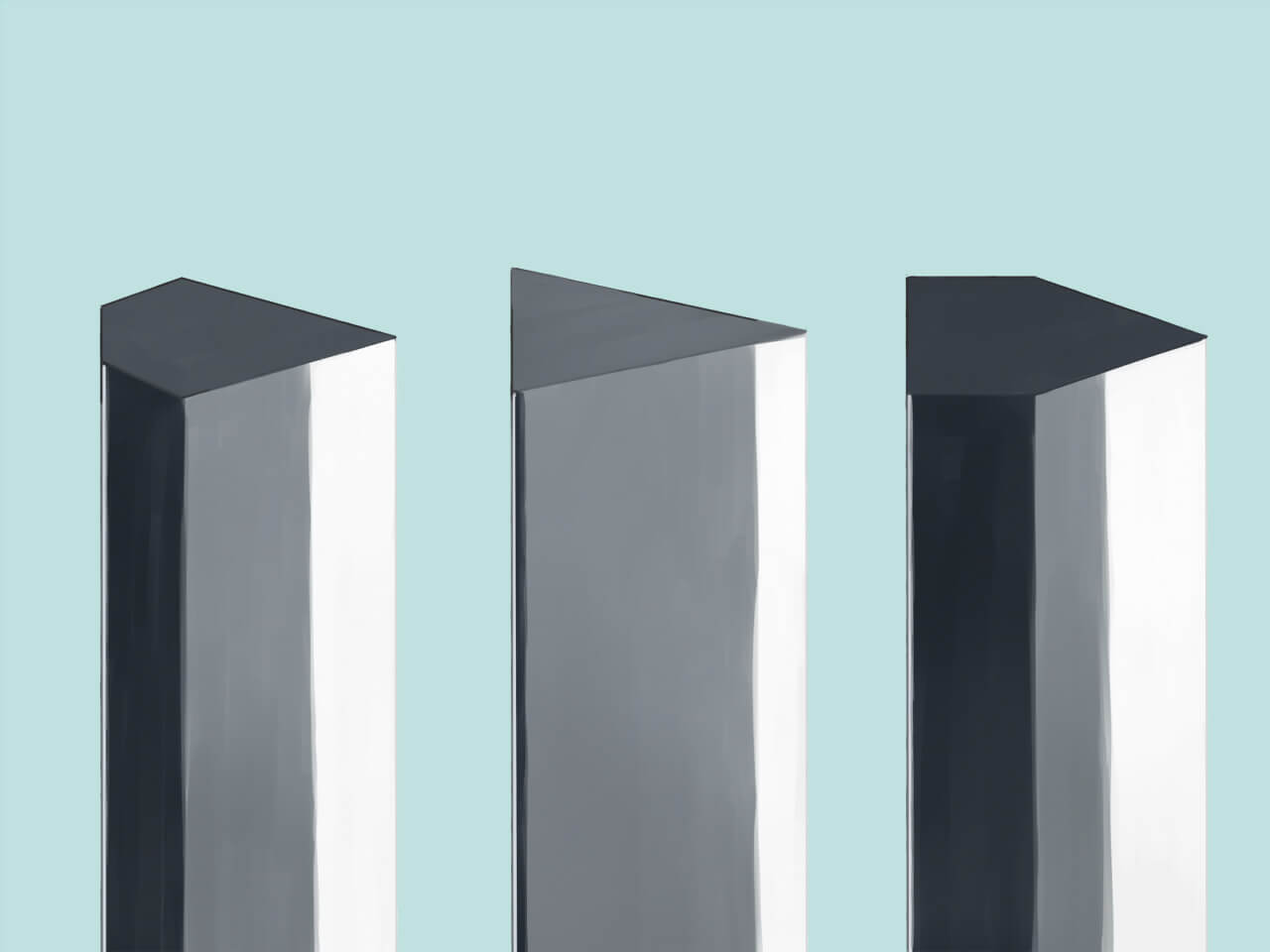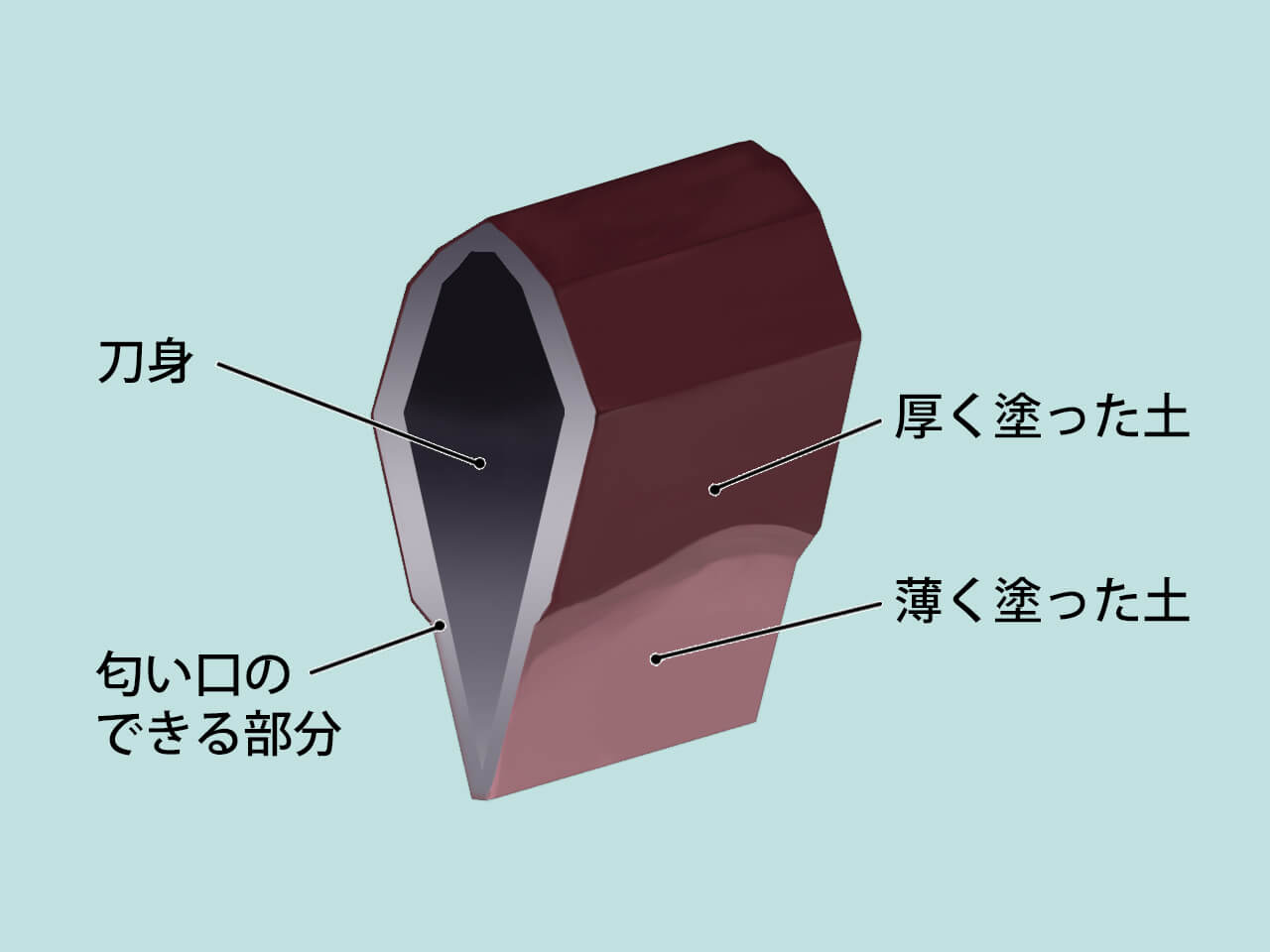続飯
そくい
やわらかめに炊かれた米をよく練って作られた糊のこと。白鞘(しらさや)を貼り合わせる際の接着剤として使われる。鞘内部に付着した錆などを除去するために、鞘を割る必要がある場合には、鞘を割ることや復元が比較的容易であることから重宝された。接着力では現代の化学接着剤の方が強力だが、割鞘直しが困難となってしまう点に難点がある。

やわらかめに炊かれた米をよく練って作られた糊のこと。白鞘(しらさや)を貼り合わせる際の接着剤として使われる。鞘内部に付着した錆などを除去するために、鞘を割る必要がある場合には、鞘を割ることや復元が比較的容易であることから重宝された。接着力では現代の化学接着剤の方が強力だが、割鞘直しが困難となってしまう点に難点がある。

製鉄炉に空気を送り込むためのふいごのこと。日本書紀において、「神武天皇」(じんむてんのう)の妻になった「媛蹈鞴五十鈴姫命」(ひめたたらいすずのひめのみこと)の名前の記述がある古い言葉でもある。その後、鉄を精錬する炉のことを「鑪」(たたら)と言うようになり、炉全体を収める大きな家屋、さらにはこれら全体を含めた製鉄工場を「たたら」と言うようになった。


鋼(はがね)を加熱し、槌(つち:物を叩く道具)で打つことによって、鋼を鍛える作業のこと。目的は、鋼を何度も折り返して鍛えることにより、粘りをもたせて強度を増すと同時に不純物を叩き出し、炭素量を平均化させること。刀匠、弟子の中でも優秀な者が務める向こう鎚が共同して作業を行なう。向こう鎚(むこうづち)が刀匠の合図に合わせて槌を打つことを「相槌を打つ」と言う。