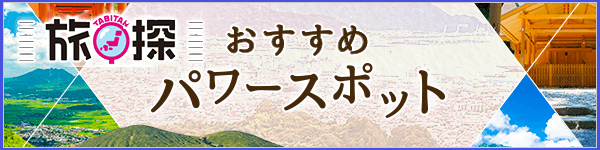1989年(昭和64年)1月7日に昭和天皇が崩御すると、皇室財産の整理が行なわれました。この中で、宮中行事で用いる屏風や刀剣類などは、皇室の財務・財政について定めた「皇室経済法」第7条に基づく「御物」として、皇室の私有財産とし、その他は国に寄付され国有財産になったのでした。三の丸尚蔵館は、設置計画当初、収蔵物の保存・研究を主目的とした収蔵庫としての機能に限定する予定で、展示については博物館や美術館に貸し出し等を行なう予定でした。その後、皇室の意向を受け、三の丸尚蔵内に展示室が設けられたのです。
三の丸尚蔵館の収蔵・展示品に国宝はありません。それは御物が慣習上、文化財保護法の対象外とされてきたためでした。国宝とは、文部科学大臣によって重要文化財に指定された物のうち、国民の宝として国として特に保護すべき物を指します(「文化財保護法」27条2項)。御物は国(宮内庁)によって保護・管理されてきた物であるため、文化財保護法の趣旨に沿っていないということなのです。しかし、国宝でないからと言って、美術品としての価値が劣ると言う訳ではありません。
御物の中で、国宝に指定されている唯一の例外は正倉院です。これは、ユネスコの「世界文化遺産」に指定されたために、建物が国宝になっています。なお、正倉院に収蔵されている宝物は、国宝ではありません。
三の丸尚蔵館には国宝級の日本刀が収蔵・展示されています。代表的な1振が「短刀 :銘正宗」。「京極正宗」の号を有するこの短刀は、豊臣秀吉が「京極高次」(きょうごくたかつぐ)に贈った物だとされています。高次の死後、子の「京極高広」が将軍家に献上しました。「正宗」の作品で、銘を切った物は非常に数が少なく、現存する物では「不動正宗」、「大黒正宗」、「本庄正宗」に、この京極正宗を加えた4振(いずれも短刀)のみです。
また銘はありませんが、同館では正宗の作品とされている「刀:無銘」も収蔵・展示されています。「若狭正宗」と呼ばれる日本刀で、呼び名は所持していた秀吉の正室北政所の兄の子、木下勝俊が「若狭少将」と呼ばれていたことに由来しています。江戸時代の鑑定士「本阿弥家」が「金千枚=一万両」の折紙を付けたことでも知られ、「不知代」(だいしらず:非常に高価で代金を付けた場合には、いくらになるか分からないこと)や「無代」(代価がいらない物。不知代同様、代金が付けられない物)を除いた正宗の作品の中では、最高額が付けられた逸品です。
 鑑定区分
鑑定区分
 時代
時代
 制作国
制作国
 刀工
刀工