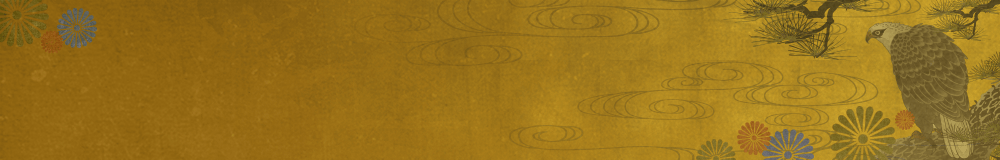もともとは密教のお寺でしたが、土肥実平が「萬年[万年]の世までも家が栄えるように」との願いを込めて「萬年山」(まねやま)と号を付け、持仏堂(じぶつどう:日常的に礼拝する仏像[念持仏]などを安置するためのお堂)を整えたのがはじまりとされています。
土肥実平一族のお墓
城願寺には、土肥実平一族のお墓66基が現存。また、境内には「1304年(嘉元2年)7月」と刻印された五層の塔や、「1375年(永和元年)6月」と刻まれた宝篋印塔(ほうきょういんとう:墓塔や供養塔に使用される仏塔の一種)など、いくつかの仏塔があります。
ひとつの墓所に各種形式・各年代にまたがる仏塔が立ち並ぶのは、関東地方において大変珍しい光景。墓所は神奈川県指定文化財に指定されており、関東有数の史跡として有名です。
七騎堂

七騎堂
城願寺には、七騎落にまつわるお堂「七騎堂」(しちきどう)があります。
このお堂で祀られているのは、安房国へと出航した①源頼朝、②土肥実平、③土屋宗遠、④「安達盛長」(あだちもりなが)、⑤岡崎義実、⑥「新開忠氏」(しんかいただうじ)、⑦「田代信綱」(たしろのぶつな)の7人。
このうち、安達盛長は鎌倉幕府で「13人の合議制」のひとりに抜擢された人物です。新開忠氏は土肥実平の息子で、土肥遠平とは兄弟の関係にありました。また、田代信綱は「田代冠者」(たしろかじゃ)と号され、源義経に従軍して「木曽義仲/源義仲」(きそよしなか/みなもとのよしなか)を追討したことで知られています。
土肥実平と土肥遠平の像
城願寺の境内には、土肥実平と土肥遠平の像が寺宝(じほう)として存在。このうち、土肥実平の像は衣冠束帯(いかんそくたい:貴族や高級官僚の正装)の姿で、腰には
刀剣を
佩刀(はいとう)。一方で、土肥遠平の像は僧衣の姿。手に持っているのは笏(しゃく)で、頭部は差し込み式(首に差し込んで固定するタイプ)となっていますが、現在は脱落防止のために漆で固定してあります。
どちらの像も、制作されたのは鎌倉時代後期から室町時代前期。制作したのは土肥氏の子孫・小早川氏で、城願寺へ安置されたと伝わります。
土肥実平が植えた「ビャクシン」

願成寺のビャクシン
願成寺にある「ビャクシン」(イブキ)は、土肥実平が持仏堂を建てた際に自ら植えたと伝わる大樹です。
高さは約20m、幹の太さは約6mもあり、関東有数の古木として国の天然記念物にも指定されています。
なお、「湯河原温泉観光協会」では土肥実平の活躍を描いた漫画のタイトルに「ビャクシン」の名を採用。この漫画冊子は、外国人や若い人達に土肥実平のことを知ってもらうために作られました。