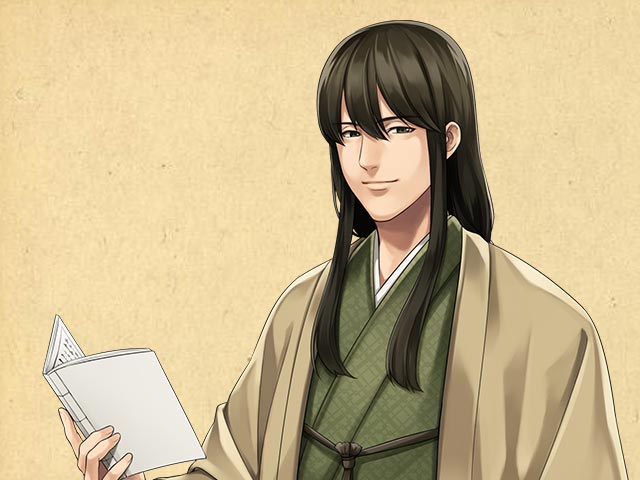武士の嗜みから生み出された吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)の本来の演目とは、詞章となる漢詩や和歌の題名がそのまま演目とされていました。吟剣詩舞が開眼された初期には、藩政時代の大名、学者、江戸末期から明治初期にかけて活躍した学者や軍人の詠んだ漢詩が詞章とされ、吟詠(ぎんえい)、剣舞(けんぶ)で表現されました。
詞章となる漢詩は、剣舞のみに使用されるものと、扇を使用する詩舞に使用されるもの、剣詩舞双方で使用されるものの三種に分けられていました。
剣舞において名作とされる作品をいくつかご紹介します。

水戸光圀
「水戸黄門」で知られる水戸藩の2代目藩主水戸光圀(みとみつくに)は、藩政だけではなく、文化、修史事業にも力を入れた大名でした。「徳川家康」の孫であり、幕政にも影響力をもつ御三家に生まれた光圀は、少年時代は素行不良で周囲を困らせます。しかし、18歳のときに「司馬遷」の「史記」を読んだ光圀は感銘を受け、以降態度を改めます。
光圀の詠んだ漢詩詠日本刀(えいにほんとう)は、吟剣詩舞の剣舞の演目として知られています。その名の通り、日本刀について詠んだ漢詩であり、簡単に人を斬り、大事な刀を汚してはならないと諌めています。武士にとって、いかに日本刀が重要な物であったのかが、この詩を通じて分かります。
光圀から7代を経た幕末、藩政改革に成功した名君で知られる9代目水戸藩主「徳川斉昭」(とくがわなりあき)もまた、優れた漢詩を残しています。

楠木正成
斉昭作の漢詩大楠公(だいなんこう)は、詩吟や吟剣詩舞の演目として有名です。大楠公とは、14世紀初頭、鎌倉時代末期から室町時代にかけ、軍事に優れた武将として知られた「楠木正成」(くすのきまさしげ)のこと。
楠木は、「後醍醐天皇」の命を受けて鎌倉幕府打倒に貢献し、1333年(元弘3年)の建武の新政を「足利尊氏」らと支えた名将です。楠木の波乱に満ちた生涯は、斉昭の漢詩以外にも能、浄瑠璃といった古典芸能の他、現在も小説などの題材として取り上げられています。
斉昭の大楠公では、楠木公の忠義の精神を称え、その名声が今後も永遠に伝えられていくと詠んでいます。詩中には、中国の五代に作られた詩の一部「豹死留皮(豹は死して皮を留む)」が引用されています。五代とは、907年の唐の滅亡から960年まで、5つの王朝が君臨した時代です。豹死留皮(豹は死して皮を留む)とは、豹は死後に美しい毛皮を残す、獣でさえそうなのだから、人は死後に名声を残さなければならないという意味。しかし、楠木公のような立派な人物の名声は今も、そしてこれからも伝えられ続けられると称賛しているのです。
明治時代には、軍人が詠んだ漢詩が詞章となりました。
長州藩士の家に生まれた「乃木希典」(のぎまれすけ)は、幼少から武術や学芸の教育を受けた武士でした。しかし、少年期には学者になることを志したほど、学芸にも秀でた人物でした。優れた陸軍大将、教育者でもあった乃木は、漢詩作においても優れた才能を発揮し、名作を数多く残しています。そのなかでも、中国の戦場跡で戦死者に向けて詠んだ「金州城」(きんしゅうじょう)、「爾霊山」(にれいざん)は剣舞の詞章としても有名です。