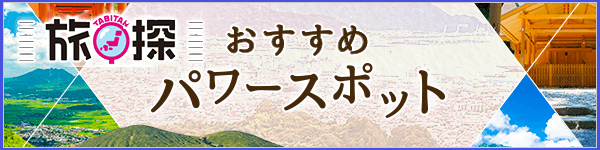神宮徴古館の歴史は、1886年(明治19年)に神宮の宮域に総合博物館を開設することを目的とした「神苑会」(しんえんかい)の発足に始まります。神苑会によって日本初の産業博物館である「神宮農業館」が創設され、その後、同館が倉田山に移設増築されると、その中の「農業館附属工芸館」を「仮徴古館」として開館。
そして、1909年(明治42年)、「赤坂離宮」(あかさかりきゅう:現在の迎賓館)などを設計した当時の宮廷建築の第一人者「片山東熊」(かたやまとうくま)設計の神宮徴古館が完成。1911年(明治44年)、設立の目的を遂げた神苑会は解散し、神宮が事業を引き継ぎました。
神宮に関係する古器、図画、文書など神宮の沿革についての資料を保存・展示し、観覧に供することを目的として運営されることとなった神宮徴古館を象徴する展示品に、20年に一度の式年遷宮で撤下された御装束神宝があります。これらの調製には飛鳥時代、奈良時代、平安時代の文化様式が垣間見られ、調製当時に使用されていた材料や技法が脈々と継承され、現在でもそのまま再現されていることが分かります。これら御装束神宝の展示を通して式年遷宮の意義を伝え、日本の文化伝統を保存・育成していくことも、徴古館の大きな目的です。
終戦間近の1945年(昭和20年)、神宮徴古館は危機に立たされます。7月29日未明の空襲によって被災。建物をはじめとして、収蔵品の約9割が焼失してしまったのです。3年後の1948年(昭和23年)に、内宮宇治橋前の参拝者休憩所を仮徴古館として再出発すると、1953年(昭和28年)第59回式年遷宮の附帯事業として開館。残存した外壁部分を活かしつつ、鉄筋コンクリート造の2階建ての建物としてリニューアルされました。そして1985年(昭和60年)には新館が竣工し、1998年(平成10年)、神宮徴古館は神宮農業館と共に、明治時代の建造物の代表的遺構として国の登録有形文化財となったのです。
神宮徴古館には、国の重要文化財に指定されている2振の刀剣が収蔵されています。ひとつは「毛抜形太刀」で、もうひとつが「有國」(ありくに)の折り返し銘がある脇差。
毛抜形太刀は、平安時代中期頃に登場した、日本刀の原形とも言われている刀剣です。当時、東北地方を本拠としていた「蝦夷」(えみし)が制作していた「毛抜形蕨手刀」(けぬきがたわらびてとう)を手本として、内国で制作が開始。主に「衛府」(えふ)の官人が佩用していました。神宮徴古館収蔵の毛抜形太刀は、「平将門の乱」(たいらのまさかどのらん)で将門を討ち取ったと言われている「藤原秀郷」(ふじわらのひでさと)が佩用していたとされる初期の物。刀身、拵がほぼ完全な形で残存している貴重な1振です。
脇差に折り返し銘がある有國は、鎌倉時代初期に山城国(現在の京都府)で活動した「粟田口派」(あわたぐちは)の刀工で、実質的な開祖と言われている粟田口六兄弟の5男。有國については現存する作品が少なく、また、在銘の物が皆無であると言われています。
神宮徴古館収蔵の脇差は、「茎」(なかご:刀身で柄の中に入る部分)を切って短くする際に、その部分を反対側に折り曲げて銘を残す手法で有國の作風を現在に伝える1振。細身の刀身で、細直刃の刃文は「山城伝」(やましろでん)の優美さがよく現れていると言える作です。
 鑑定区分
鑑定区分
 時代
時代
 制作国
制作国
 刀工
刀工