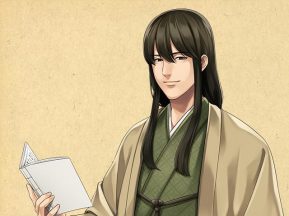明治時代より以前、吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)という芸道が確立されていなかった封建時代、剣舞(けんぶ)は武士層が宴席や婚礼の席などで披露する「嗜み」でした。宴席の主旨にふさわしい漢詩の吟詠(ぎんえい)に合わせて、剣舞の素養をもつ武士は刀剣を抜き、舞を出席者に披露。自らのアイデンティティの象徴である刀剣は、武士達にとって相棒以上に緊密な存在でした。
そして、武家社会が解体された明治時代、職務と地位、そして帯刀する権利を失った旧武士達は、従来とは異なった方法で日本刀との繋がりを保ったのです。
明治時代の新聞記事や小説には、しばしば「撃剣興行」(げきけんこうぎょう)という言葉が登場します。撃剣興行とは、木刀や竹刀を使用した剣士の対戦を、寄席や大道芸として木戸銭を得て興行したものです。東京・浅草や横浜にあった寄席などで当時盛んに催され、大人気となりました。

榊原健吉
撃剣興行とは、剣術家の榊原健吉(さかきばらけんきち)が職を失い困窮する旧武士の救済を目的として興したもので、興行の木戸銭を旧武士の収入としたのです。
榊原は、旧幕府講武所の師範役を務めた剣士でしたが、明治維新がもたらした旧武士達の窮状を解消するため、1873年(明治6年)に東京・浅草で「撃剣興行会」(げきけんこうぎょうえ)を始めます。撃剣興行は、時の東京府知事「大久保一翁」(おおくぼいちおう)が許可を下し、旧幕臣らと親しかった侠商(きょうしょう)「三河屋幸三郎」(みかわやこうざぶろう)、浅草専念寺の住職・田沢俊明らの後援を得て、興されました。
浅草と横浜で好評を得た撃剣興行は、瞬く間に流行し、東京府(現在の東京都)には30以上の興行小屋ができたという当時の記録が残されています。その後も流行は広がり、日本各地で興行が行なわれました。
しかし、短期間に広まった撃剣興行の人気は、すぐに終焉を迎えます。急激に拡大する人気に即し興行も増加しましたが、優れた出演者の数が限られていたため、舞台の質が低下。さらに、剣術の素養のない観客には勝敗の判定が不明瞭であったため、次第に客離れが起きたのです。
興行としての価値を失った撃剣ですが、その後は警察庁での警官の鍛錬に採用され、撃剣興行の剣士達の多くが警察官として登用されました。
一方、剣術、武士道精神の継承を目指した旧武士、剣術士達は吟剣詩舞を開眼します。1890年(明治23年)「日比野雷風」が開眼した神刀流の吟剣詩舞を始まりとして、その後派生した多くの流派では、吟剣詩舞を剣術の技と精神を芸道として昇華したものとして門下生に教えます。そのため、吟剣詩舞は寄席とは異なり、神社での奉納公演、武道場での大会、劇場などで披露されました。
また、時の天皇陛下や政治家、軍の高官、外国の来賓、実業家などの主催する舞台などでも吟剣詩舞は披露され、日本武道を礎とする芸道として鑑賞されたのです。
1908年(明治41年)には、日比野雷風が主演を務め、剣舞や吟詠を披露するサイレント映画が制作、公開されています。この映画にはストーリーは無く、雷風の剣舞を映像としてまとめた作品であり、映画館で上映されました。
一方、明治時代に発刊された会社員向けの書籍には、吟剣詩舞を宴席で披露することを勧める紹介記事が掲載されています。書籍では、会社の関係者や客との宴席で、余興として吟剣詩舞を披露できるよう、日頃から嗜むことを勧めているのです。吟剣詩舞として確立されたあとにも、剣舞は依然、宴席で披露されることが多い芸道でした。