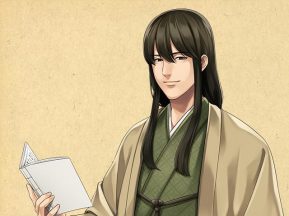剣舞(けんぶ)を舞台芸術へと昇華した日比野雷風は、文明開化によって「武士道精神が消滅」してしまうことを危惧する皇太子の御附武官・杉山直弥大佐に促され、武術と武者としての精神を宿す新たな剣舞を創造することに取り組みました。
以降、剣術や居合術などの古武道を深く、広く研究した雷風は、吟詠(ぎんえい)に合わせて剣術、武術の型を取りこんだ剣舞を舞う神刀流剣武術を開眼。吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)の普及を通じて、雷風は人々に古武道の素養とそこに宿る精神への興味を喚起し、継承することを目指しました。
しかし、杉山大佐が消失を危惧した武士道精神とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。

新渡戸稲造
欧米との親善に尽力した教育者・新渡戸稲造がアメリカで発行し、その後広く諸外国でも紹介された英文の著書「武士道」にその概要を見ることができます。
武士道とは、武士が統治した封建社会において形成、尊重された道徳倫理です。日本独自の道徳倫理である武士道は、仁・義・礼・智・信・忠・誠と名誉を重んじ、厳しく自己を律するものであり、武士=男性だけではなく、武家社会の子女にも求められた人として生きる姿勢を表しています。
主君に対して、御家人が仕えることを基本構造とする武家社会を継続していくためには、個人を優先するのではなく、主君への忠義や社会との調和、社会的責任を重視する武士道の精神が必要不可欠でした。
武士が腰に差す大小の二刀は、自身の身分、忠義、名誉の象徴であり、武勇の証し。しかし、武具である刀を常に携帯する者には、相応の責務もあり、厳しい道徳倫理感を併せ持たねばなりません。また、一振りで人を斬り倒すことのできる日本刀は、むやみに振りかざして良い物ではないのです。
武具を常に携帯する行政官僚として、武士達が形成し、遵守した道徳倫理感を欧米諸国に紹介したのが、新渡戸の武士道。新渡戸の著述を通じて武士道を知った欧米諸国の人々は、その高潔で真摯な道徳倫理に驚き、深い感銘を受けました。
吟剣詩舞を誕生へと導いた杉山直弥大佐、重野安釋博士、彼らに教示され神刀流剣武術を開眼した日比野雷風は、個人主義が優先されつつあった藩政崩壊後の日本において、武士道という優れた道徳倫理が消失することを憂い、武術の修得を通じて武士道の精神を継承しようと試みました。彼らは一様に、武士道精神を日本人の美徳として尊重していたのだと考えられます。
雷風が開眼した神刀流剣武術に融合された武術には、戦闘技巧としての側面だけではなく、武士道の倫理観に沿った多くの規律や作法が存在します。そのため、吟剣詩舞を修得しようとする者は、武術の鍛錬を通じてそこに息づく規律や法、武者としての精神も養われることを期待したのです。
舞台芸術である一方、吟剣詩舞は日本人独自の精神世界を表現する、伝統的芸道でもあります。