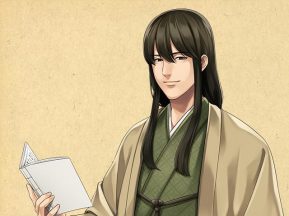音楽としての吟詠
単独の芸道としての詩吟は、明治時代初期に学問所や藩校での漢詩文教育が始まりとされていますが、大正から昭和にかけて、木村岳風(きむらがくふう)や真子西洲(まなごさいしゅう)を始めとする名手達の活躍により発展しました。なかでも「近代吟詠の祖」とされる木村岳風は、日本各地を訪ねて土着の詩吟を研究し、独自の吟法を確立、その普及活動を積極的に行ないました。1936年(昭和22年)、木村は「日本詩吟学院」を設立し、後進の育成に尽力しました。
こうした先人達の情熱的な努力の結果、現在では数百とされる詩吟の流派、宗家が存在しています。
詩吟では流派ごとに異なる吟詠法が提唱されていますが、格調高い吟詠法をとる文士調、幕末の志士達の悲しみや怒りを激しく吟ずる勤皇調という吟調は各流派とも取り入れています。この2つの吟調を中心として、様々な調性、吟法を取り込み、流派毎に積極的な活動が展開されています。
詩吟とは、定型の漢詩にリズムや諧調を付けて詠ずるものですが、日本では推古天皇の治世であった618年までに詠われた漢詩に型は存在しませんでした。しかし延喜時代(901~923年)に作られた漢詩は定型で詠まれるようになり、文字数から五言絶句(ごごんぜっく)・七言絶句(しちごんぜっく)・七言律詩(しちごんりっし)・五言排律(ごごんはいりつ)・七言排律(しちごんはいりつ)などの形式が誕生し、詩吟ではその定型の中の一部の音を伸ばして節を付けます。
吟剣詩舞の詞章としての吟詠には、漢詩だけでなく、和歌や近代詩も取り入れられていますが、いずれもその詩の情景、心情を表現するために詩吟と同様に詩文の中の一部の音を伸ばして節を付け、さらに言葉毎に強弱を付けて詠まれます。
吟詠で使用される音階はミ、ファ、ラ、シ、ドの5音からなり、その詩にふさわしいテンポ、リズムに乗せて詠われます。
そして、吟ずる際には美しく明瞭な発音で行なうことが重要視され、歯切れよく、詠っている内容が明確に伝わるように発音することが提唱されています。同様に、言葉のイントネーションについても注意が促されており、正しいイントネーション、アクセントで吟ずるよう求められます。
さらに、詩文のストーリー展開、起承転結に合わせて、全体的な変調、強弱の付け方などを調整し、詩文の中での「間」の置き方、言葉の余韻の調整も、表現する上では熟慮するよう勧められています。
吟剣詩舞の舞台上では、詞章を詠じる吟詠者は演目に即した正装または礼装を身に付け、慎み深く毅然とした姿勢を保ち、真摯に吟詠を披露します。
吟詠者と演者は詩文のもとに一体となり、それぞれに補完し合いながら詩文の世界観を表現しなければなりません。吟詠の変調に即して、演者の舞の所作や強弱も瞬時に変化し、詞章と舞が一体となって詩の世界観を表現する様子は、漢詩を解さない人にも深い感動をもたらします。
剣舞と詩吟、武士の芸事が融合し発展した吟剣詩舞には、潔く、美しく生きようとした武士達の美学が今も息づいています。