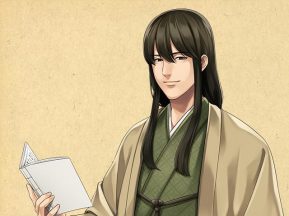明治半ば、日比野雷風(ひびのらいふう)を始めとする剣士達が創始した吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)は、誕生から120余年を経て現在も発展を続けています。
本来、吟剣詩舞は礼節を重んじる武士の精神、剣術の素養、和歌、漢詩の詩情に対する深い理解といった、武家社会の教養、精神性に端を発した伝統芸道であり、舞や舞台所作には厳しい作法が定められていました。
その後の発展とともに吟剣詩舞には数多の流派が誕生しますが、いずれの流派も礼節や芸道への真摯な姿勢については、同様の厳しさを重視していました。
しかし、近年では詞章となる詩文の選択や舞、舞台設定などに多様な変化が見られるようになります。

21世紀の吟剣詩舞
まず詞章では、吟剣詩舞においては和歌、漢詩の吟詠(ぎんえい)のみを詞章としていましたが、琴、尺八、三味線などの和楽器での演奏や、シンセサイザーの演奏などが加わる演目が増えてきています。
また、詩文にも大きな変化がもたらされ、小説の登場人物や実在した戦国武将が登場する物語や、古代ギリシャの哲学者と日本の思想家が語り合う物語などといった新作が数多く作られています。
なかには、アニメや漫画を題材にした新作も登場し、時代や背景に多種多様なテーマをもつ詩文が採用されています。
舞台の形式にも変化が見られ、多数の吟詠者が一斉に吟詠する合吟(ごうぎん)と、複数の演者が揃って舞いを披露する群舞(ぐんぶ)での演目が、大会やコンクール、クラブ活動の発表会などといった機会にしばしば選ばれています。合吟は詩吟道においてはかねてより採用されていましたが、併せて披露される剣舞(けんぶ)の群舞は近年増えてきたもので、観客を圧倒するほど迫力満点です。
そして、装束や舞台装置も変わってきています。本来の吟剣詩舞は、舞台では和服の礼装を着用し、刀剣やたすきなど、最小限の小物を使用して演目が披露されていましたが、昨今では演劇や歌舞伎にも劣らない装束、化粧を施した演者が増えているのです。
例えば、能や歌舞伎でも演目となっている義経、弁慶が登場する舞台では、武将姿の義経、法師装束の弁慶に扮した演者が舞を披露。装束だけでなく、鬘(かつら)、化粧も施しての剣舞は迫力満点、かつ勇壮で見ごたえある舞台となっています。
舞台装飾に関しても新たな手法が導入されており、大道具や背景の書割(かきわり)を使用する演目も増えています。従来の吟剣詩舞の舞台は、背景は緞帳(どんちょう)や屏風などを配しただけが主流でしたが、物語などを詩文とする演目では、各章に沿った背景や書割が舞台上に設置され、演者の舞を引き立てます。
他の舞台芸術と同様に、現代の吟剣詩舞でも照明の使用が一般的ですが、演目の起承転結に即した照明の切り替えを行ない、テーマの詩情、芸術性を補完する演出として舞台を盛り上げています。