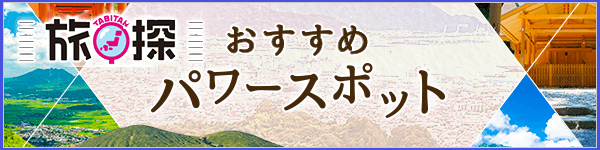出雲大社に祀られている大国主大神は、日本各地を開拓すると共に民に対して農業・漁業・殖産・医薬などの方法を伝え、国づくりを行ないました。このような心配りによって、「葦原中津国」(あしはらのなかつくに)は、「豊葦原瑞穂国」(とよあしはらみずほのくに)と称えられる豊かで力強い国へと発展します。
そののち、豊葦原瑞穂国を「天照大御神」(あまてらすおおみかみ)に返還した大国主大神は、そのときに造営された「天日隅宮」(あめのひすみのみや)に鎮座。その神殿の高さは約48mとも言われている壮大な物で、「古事記」や「日本書紀」には、屋根の両端で交差している「千木」(ちぎ)が雲を貫くほどの高さを誇っていたとの記述があるほどでした。
2000年(平成12年)出雲大社の境内遺跡から、この伝説が本当にあった可能性を示す物が発見されました。それは直径が最大約3mにも上る「宇豆柱」(うづばしら)と直径の最大が約6mになる柱の穴。これらが巨大な社殿の設計図と言われている「金輪御造営差図」(かなわのごぞうえいさしず)に描かれていた物と符合していたのです。
現在の出雲大社の本殿は1744年(延享元年)に行なわれた「延享の造営」(えんきょうのぞうえい)で造営された物で、高さは約24m。神社建築では、日本一の規模を誇る「大社造」(たいしゃづくり)の社殿は、国宝に指定されています。
出雲地方は、古来豊富で良質な砂鉄を利用した鉄の一大産地として知られ、遅くとも古墳時代後期には製鉄が始まったと言われています。
そして、平安時代になると出雲から伯耆の国境にかけて刀工集団が出現し、「たたら製鉄」によって得られた「玉鋼」(たまはがね)を原料として「日本刀」作りが行なわれるようになりました。出雲と刀剣のかかわりにおいて、特に有名なのが「ヤマタノオロチ伝説」。「素盞嗚尊」(すさのおのみこと)が出雲国(いずものくに:現在の島根県)において、「ヤマタノオロチ」を退治した際に、尾の部分から出現したとされる「天叢雲剣」(あめのむらくものつるぎ)は、のちに名を「草薙剣」(くさなぎのつるぎ)と改められ、皇位のしるしとして歴代天皇によって受け継がれる「三種の神器」のひとつとなったのです。
出雲大社の社宝が収められている「宝物殿」(ほうもつでん)では、数多くの日本刀を所蔵。なかでも国指定重要文化財の「太刀:銘 光忠」(たち:めいみつただ)が有名です。この太刀は、元々「豊臣秀吉」(とよとみひでよし)の佩刀(はいとう)でしたが、1609年(慶長14年)の遷宮の際に、「豊臣秀頼」(とよとみひでより)と、その母「淀殿」によって寄進されました。
作者の光忠は、中世において備前国(現在の岡山県)で栄えた「長船派」の実質的な祖とされる刀工で、鎌倉時代中期に活動。その作品は、鎌倉幕府が全国に命じて切れ味の優れた日本刀を注進させた「注進物」(ちゅうしんもの)の名簿にも名を連ねたほどの切れ味と共に、華やかさも兼備しているのが特徴で、「織田信長」(おだのぶなが)も光忠の作品を好んで収集していたと言われています。
 鑑定区分
鑑定区分
 時代
時代
 制作国
制作国
 刀工
刀工