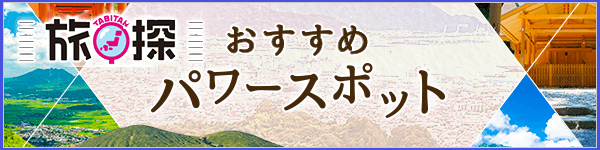一関地方では、古代において日本刀のルーツと言われている舞草刀の制作が行なわれていたと言われています。中世においては、「中尊寺」の領である「骨寺村」(ほねでらむら)の開発や葛西氏400年の統治、近世においては仙台藩・伊達氏やその支藩である一関藩・田村氏が藩制を展開。学問分野でも、儒学者や蘭学者を輩出した「大槻家」に加えて「建部家」を中心とした蘭医学、さらには「千葉家」を中心とした「和算」(日本独自に発達した数学)が大きな発展を遂げるなど、個性的な文化が隆盛を極めました。これらの一関地方の歴史や文化を取り上げ、解明して後世に承継すべく設立された博物館。それが一関市博物館です。
1997年(平成9年)に設立された一関市博物館では、「地域の歴史」、「舞草刀と刀剣」、「大槻玄沢と蘭学」、「大槻文彦と言海」、「一関と和算」、「地域の美術工芸」の6テーマが設定されており、資料の収集・整理が行なわれ、後世に承継すべく保存・展示がされています。常設展示では、上記の6テーマのうち「地域の歴史」と「地域の美術工芸」を除いた4テーマに、新たに「一関のあゆみ」を加えた5テーマについて展示されています。これらのテーマについて、地域の歴史と文化の変遷を考慮しながら多様な資料を展示することで、各テーマについて系統を立てて理解できるように工夫が施されていることが、一関市博物館の大きな特徴です。
一関市は岩手県南部に位置しており、隣町には世界遺産となった「中尊寺」があり、経蔵の荘園「骨寺村」が存在したことなど奥州藤原氏ゆかりの地域と言えます。平安時代中期、一見、日本刀とは無縁とも思えるような場所で日本刀のルーツのひとつと言われる物が生み出されました。それが舞草刀です。
その特徴は刀の反りにあると言われています。当時、日本で作られていた真っすぐな刀の「直刀」とは違い、舞草刀には刀に反りがある点が特徴です。この反りこそが、日本刀のルーツと言われている所以。古墳時代に東北地方に住んでいた「蝦夷」(えみし)が作っていたと言われている「蕨手刀」(わらびてとう)にも若干の反りが見られることから、舞草刀は蕨手刀の影響を受けたのかもしれません。いずれにせよ、「舞草鍛冶」は画期的な日本刀を作り出したのでした。
舞草鍛冶は、「観音山」中腹周辺で集落を形成していたと考えられています。この地は、良質で豊かな砂鉄、水、燃料に恵まれており、日本刀を作る下地は整っていました。北上川を挟んだ対岸に奥州藤原氏の居館が存在しており、奥州藤原氏によって築かれた平泉文化は、常に最高の物を追求していく考え方があったと言われ、それは日本刀などの武器においても同様でした。
日本刀に関する古伝書「観智院本銘尽」(かんちいんぼんめいづくし)には、舞草鍛冶8人の名前が記されており、舞草鍛冶が刀工として名刀と呼ばれる日本刀に比肩するクオリティの物を作り出していたことが分かります。舞草鍛冶は、奥州藤原氏お抱えの刀工であったと言えますが、奥州藤原氏の滅亡と共に、衰退を余儀なくされ、鍛冶達は全国に散らばっていきました。
 鑑定区分
鑑定区分
 時代
時代
 制作国
制作国
 刀工
刀工