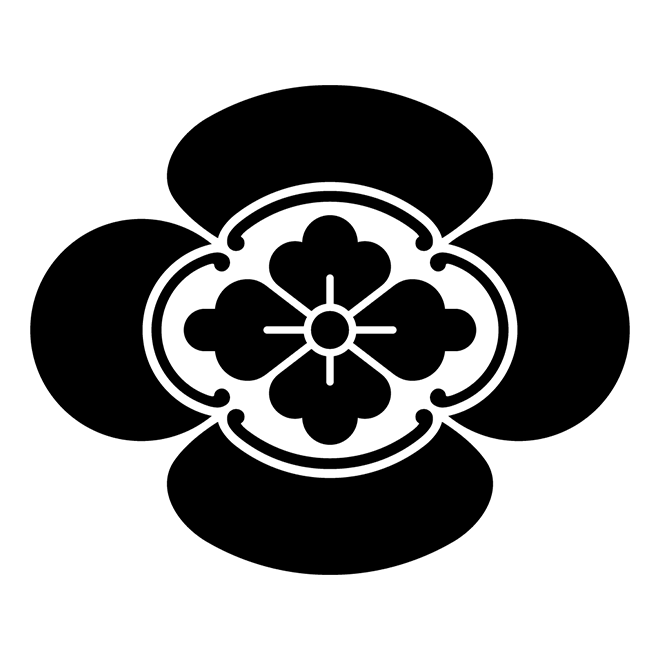
「木瓜紋・窠紋」は、御簾(みす)の上に付く絹織物の帽額(もこう)に付けられた円形の文様である木瓜(もっこう)をモチーフにした紋。正式名称は窠(か)と言い、大型の鳥の巣を象った図です。
木瓜紋は奈良時代には文様として使用されるようになりました。輪状の外郭、その内側にある細い輪状の内郭、中心部の3部分からなる図で、輪状の部分は3~8の組み合わせがあり、内郭をもたないデザインもあります。中心部には唐花が描かれることが多いです。
多くの氏族の家紋として使われている「5大家紋」のひとつでもあり、平安時代末期に公卿の「徳大寺実能」(とくだいじさねよし)が家紋に設定。その後武家にも広まり、15世紀初頭には多くの家が木瓜紋・窠紋を使用していました。また、木瓜は「きうり」と読めることなどから、きゅうりが由来だと思われていたと言うエピソードも存在。このような事情から、木瓜紋を神紋とする神社では、祭礼期間中はきゅうりを食べないといった風習も生まれました。
木瓜紋は「織田信長」が使用した家紋としても有名。織田家が使用したのは、織田信長の父「織田信秀」(おだのぶひで)が主君の斯波氏(しばし)から下賜(かし:身分の高い人が、身分の低い人に与えること)されたことに由来するとされています。また、「五瓜に唐花」(ごかにからはな)は「八坂神社」(京都府京都市東山区)の神紋としても用いられる紋で、関連する神社で全国的に使用されました。
























