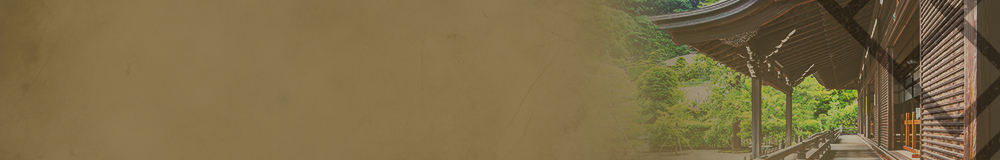一幡の誕生
「一幡」(いちまん)は、1198年(建久9年)、源頼家のもとに生まれました。
源頼家は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の嫡男。そのため、長男である一幡は、源頼朝の嫡孫にあたります。源頼朝にとって待望の初孫であった一幡には、同幕府における征夷大将軍の座に就く将来が待っていたかもしれません。
しかし、そんな一幡の運命は、母親である「若狭局」(わかさのつぼね)の出自が要因のひとつとなって一変します。
一幡が誕生した翌年の1199年(建久10年)、源頼朝は出家したわずか2日後に死去。これに伴って一幡の父・源頼家が家督を相続し、鎌倉幕府2代将軍に就任しました。
ところが、1203年(建仁3年)7月、一幡が6歳の頃に、源頼家が重い病に突如倒れてしまい、その約1ヵ月半後に危篤状態に陥ります。このときに問題となったのが、源頼家に万が一のことがあった場合に、誰が家督を相続して次期将軍になるかということ。順当に行けば、一幡が源頼家の跡を継ぐはずです。実際、病に臥せた源頼家自身も、家督のすべてを一幡に譲ろうとしていました。
しかし、一幡の母・若狭局は、源頼家を幕政において補佐するために13人の有力御家人によって敷かれた「13人の合議制」のメンバー、「比企能員」(ひきよしかず)の娘。一幡がこのまま次期将軍に決まれば、13人の合議制における比企能員の立場が一気に有利となります。
これを恐れたのが、当時、初代執権として幕府の実権を握っていた「北条時政」(ほうじょうときまさ)です。北条時政は、源頼家と10歳ほど年齢が離れた弟、「千幡」(せんまん:のちの3代将軍・源実朝[みなもとのさねとも])の後見人を務めていました。
そのため、一幡ではなく千幡を次期将軍に立てることで、自身の執権としての立場を揺るがないものにしたいと考えたのです。
この比企能員と北条時政の対立は、「比企能員の変」と呼ばれる政変にまで発展。「吾妻鏡」(あずまかがみ/あづまかがみ:同音で東鑑とも表記する)によれば、源頼家が危篤状態と判断された際に、家督継承の措置として一幡には関東28ヵ国の地頭職、千幡には関西38ヵ国の地頭職を分割相続させることが決定します。
これを知った比企能員は激怒し、娘の若狭局を通じて源頼家に報告。その後、比企能員は源頼家と共に、北条時政と千幡の暗殺を計画したのです。しかし、この計画は事前に北条氏へ知れ渡ることとなり、比企能員は北条時政に呼び出され、誅殺されてしまいます。
最終的には、一幡が住んでいた小御所(こごしょ)が北条氏率いる大軍から襲撃を受け、比企一族は滅亡。このとき一幡と母・若狭局は、比企一族と共に焼死したと伝えられています。