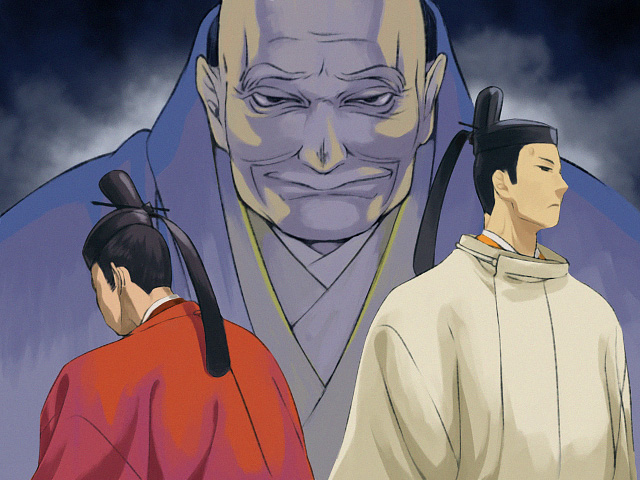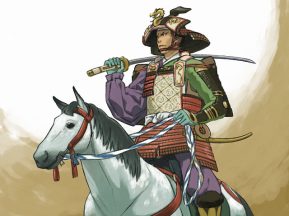鵜丸を授けられる源為義
源為義(みなもとのためよし)は、保元の乱で崇徳院側に付いた武将です。崇徳院が源為義を傘下にした場面は、保元物語の「新院[崇徳院]源為義を召さるる事」に描かれています。
不安定な情勢のなかで身の危険を感じた崇徳院は、数人の家臣を連れて、それまでいた鳥羽の田中殿(京都府京都市)から、妹・統子内親王(むねこないしんのう)の御所(ごしょ:天皇をはじめとした、特に位の高い貴人の邸宅)である白河殿(しらかわどの:京都府京都市)に身を寄せました。
白河殿に入った崇徳院らは、その夜に六条にいる源為義を呼びますが、「味方する決心が付かない」と言い放ち、やって来ません。そこで藤原教長(ふじわらののりなが)を遣わせると、源為義はこう言いました。
「私はかねてより帝にお仕えしていますが、実戦に出たことは2度しかありません。1度目は14歳のとき、大伯父の美濃守義綱(みののかみよしつな)が朝敵(ちょうてき:朝廷の敵)となって近江の甲賀山に立てこもっていたのを攻め、合戦では各所で勝利し、美濃守義綱を投降させました。2度目は18歳のとき、宣旨(せんじ:天皇や太政官の命令を伝達する文書)をいただいて、比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ:滋賀県大津市)を攻めようとしていた奈良の僧侶達を追い返しました。他に騒乱が起こったときは、若い者を派遣して鎮圧させていたため、私自身は武の道に通じていないのです。私の嫡子である源義朝(みなもとよしとも)は、坂東(関東地方)育ちで弓矢を極め、源義朝に付き従う者達は皆関東の強者達です。しかし源義朝は、後白河天皇に呼ばれて参上しています。源義朝の他にも子どもは多数いますが、大将を任せられる者はいません。けれど八男の源為朝(みなもとのためとも)は九州で育ち、弓矢や刀の腕も立ちます」。
さらに源為義は「源為朝は乱暴者だったために、豊後国(大分県)の尾張権守家遠(おわりごんのかみいえとお)を後見に、13歳の10月から15歳の3月まで大きな戦を20余り経験させ、城攻めや戦略を学ばせたところ、3年で九州の武士達を従えるようになり、惣追捕使(そうついぶし:治安維持にあたる役職)に就いて6年が経ちました。その間、源為朝の狼藉(ろうぜき:乱暴なふるまい)のせいで私は役職を解任されたこともあり、推薦するにはおこがましいですが、ちょうど源為朝はここへ来ているので、私の代わりに参上させましょう」と続けました。
源為義が大将を辞退した理由は他にもありました。夢のなかで先祖代々受け継ぎ守ってきた8領の鎧が、風に吹かれて散り散りになるという不吉なお告げがあったのです。
それに対して、教長は「夢で見たからといって、本当に武具が壊れることがあるか。あなたの言い分は、崇徳院のもとに参上して申し上げるべきこと。この場で返答するのはいかがなものでしょうか」と苦言を呈しました。
源為義は「恐れ多いことだ」と言い、6人の子ども達を連れて参上。崇徳院はそれを評価して、美濃国青柳庄(みのこくあおやぎしょう:岐阜県大垣市)と近江国伊庭庄(おうみこくいばしょう:滋賀県東近江市)を源為義に与え、判官代(ほうがんだい:上皇に仕える役人)に任じました。
そして崇徳院は「上北面(じょうほくめん:院の御所を警備する詰所)に控えていなさい。また源為義の息子の源頼賢(みなもとのよりかた)は、蔵人(くろうど:朝廷の機密文書の保管や伝達、宮中の行事や事務を行なう者)に任じよう」と言いました。
これが、崇徳院が源為義を配下に置いた経緯です。保元物語は語られるうちに改作され、新たな記述が追加されているものがあります。「流布本」(るふぼん)と呼ばれる、比較的最近成立した文献の中では、鵜丸の由来について、見出しも内容に合わせ「新院源為義を召さるる事附たり鵜丸の事」と書かれています。
元々鵜丸は、白河院の手元にあったとされています。白河院が神泉苑(しんせんえん:京都府京都市)に出かけ、宴遊ののちに「鵜飼」に遭遇します。
すると1羽の鵜丸が、2~3尺(60~90cm)の物を何度も咥えては落とし、咥えては落としていたのです。何かと思い、咥え上げた物を見ると、それは長覆輪(ながふくりん:柄頭から石突きまでを金や銀で飾った物)の太刀でした。
白河院は、その太刀を鵜丸と名付けて持ち帰ったとされています。そして鵜丸は、白河院から鳥羽院へ、鳥羽院から崇徳院へ受け継がれ、源為義の手に渡りました。
その後、鵜丸が保元の乱で活躍したのかどうか、具体的な記述はありません。保元の乱は後白河天皇派に軍配が上がり、崇徳院派の源為義は、敵方として戦った源義朝に首を切られて亡くなりました。
代々天皇に受け継がれた由緒正しき名刀鵜丸。鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」(あずまかがみ)によると、戦乱の中で一時失われながらも、九州で戦後処理をしていた源範頼(みなもとののりより)によって発見され、再び朝廷に献上されました。
しかし現在の所在は不明であり、その姿を観ることが叶わない刀剣のひとつです。
比叡山 延暦寺旅探では「比叡山 延暦寺」をはじめ、日本全国の観光名所を検索できます!