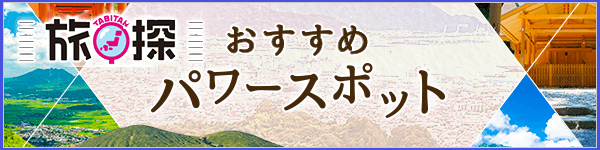※この写真は彌彦神社宝物殿様からご提供いただいております。
-
-
 鑑定区分
鑑定区分
- 重要文化財
-
-
-
 時代
時代
- 室町時代
-
-
-
 制作国
制作国
- 備前国
-
-
-
 刀工
刀工
- 長船家盛
-
- 日本刀解説
- 銘 南無正八幡大菩薩右恵門烝家盛/南無唵摩利支天源定重 応永廿二年十二月日