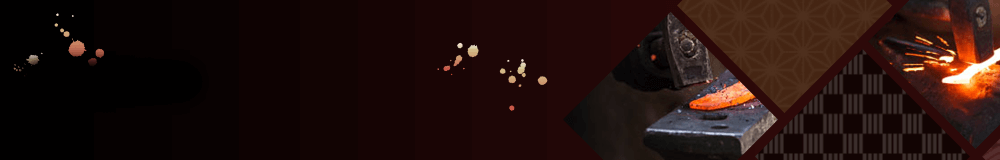「月山貞一」(がっさんさだかず)は1836年(天保7年)、近江国(現在の滋賀県)で塚本家の子として誕生。7歳のときに大阪で活躍していた刀匠「月山貞吉」(がっさんさだよし)の養子となりました。
11歳から刀工の修業を始めた貞一の上達はめざましく、1851年(嘉永4年)16歳のときに「月山貞吉造之嫡子貞一十六歳ニ而彫之、嘉永四年八月吉日」と銘のある平造りの脇差を作刀。鍔(つば)に滝不動(滝と不動明王を配する日本の伝統的な構図)が彫られたこの脇差の完成度は高く、貞一に作刀の才能があったことが見て取れます。
明治に入り1876年(明治9年)に廃刀令が施行されると、日本刀の需要が激減。多くの職人が転業を余儀なくされる中、貞一は作刀一筋に生き、1906年(明治39年)当時の刀匠として最高の名誉であった「帝室技芸員」に任命されました。
帝室技芸員となり宮内省御用刀匠となった貞一は、愛刀家として名高い明治天皇の軍刀をはじめ、皇族や著名人の刀剣を作刀し、刀匠界にその名を残します。
貞一の作風は、全体としては豪快な造込みの物が多く、「綾杉肌」(あやすぎはだ)と呼ばれる大きく波を打ったような形状の鍛肌(鍛錬によりできる地鉄の模様)を得意としました。
また、刀身彫刻の名人としても知られ、濃厚で緻密な彫物を刀身に施す「月山彫り」という技法を大成させています。