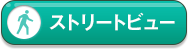「刀剣博物館」は刀剣・日本刀を保存・公開し、「日本刀文化」の普及を目的として1968年(昭和43年)に「日本美術刀剣保存協会」の付属施設として開館。2017年(平成29年)3月31日に代々木にあった旧博物館を閉館し、2018年(平成30年)1月19日から両国で新たに開館して、展示が再開されました。刀剣・日本刀は、単なる武器ではなく、権威の象徴や美術品としての側面も有しています。そのような日本刀文化を広く発信していく役割を担っている博物館です。
- 最新情報
- 刀剣の基礎知識
- 刀剣・日本刀
- 刀剣・日本刀動画
- 刀剣・日本刀を学ぶ
- 刀剣事典
- 刀剣関連施設
- 刀剣ワールド/剣
- 刀剣ワールド/甲冑
- 刀剣ワールド/鉄砲・大砲
- 合戦武具/書画・美術品
- 合戦・戦国史を知る
- 刀剣浮世絵・城サイト
-
刀剣キャラ・刀剣エンタメ
- 刀剣キャラクター
- 刀剣イラスト集
(刀剣キャラ) - 刀剣キャラクター
塗り絵 - Web歴史小説
刀剣三十六遣使 - 刀剣キャラクターめんこ
- キャラクター
刀剣メッセージカード - 刀剣マンガ
(刀剣ことわざ4コマ漫画) - 刀剣アニメ「千年樹」
(刀剣ミュージック) - 日本の歴史川柳
- 刀剣ワールドカレンダー
- 刀剣ワールド壁紙
(待受画面) - 鬼滅の刃 特集
- モンハンライズ
と刀剣 - 刀剣ゲームアプリ
- ファンタジーに
登場する剣 - 刀剣コスプレ
- 刀剣コスプレ写真集
- 刀剣界ガイド
- 「刀剣ワールド」サイトへ一発アクセス!
- 刀剣広場
- 刀剣・日本刀絵葉書・
甲冑(鎧兜)絵葉書 - イラスト・塗り絵
コンテスト - 刀剣コスプレ写真
コンテスト - 武将銅像写真
コンテスト - 寺・神社写真コンテスト
- 博物館・美術館・科学館
写真コンテスト - 御朱印・御城印 写真コンテスト
- その他コンテンツ
- すべてを見る
- 刀剣ワールドトップページ