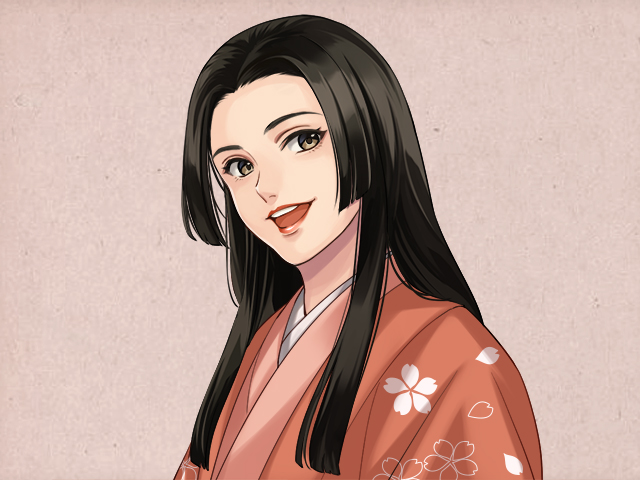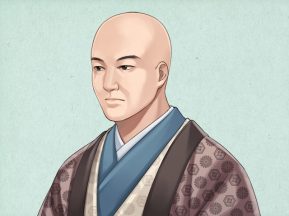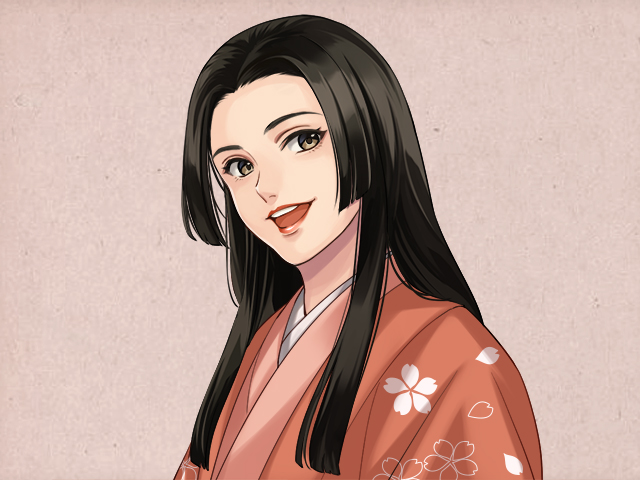
糸姫
「糸姫」は、1571年(元亀2年)に「蜂須賀正勝」(はちすかまさかつ:別名・蜂須賀小六[はちすかころく])の次女として誕生します。
蜂須賀正勝は「豊臣秀吉」(とよとみひでよし)の家老(かろう:重臣)であったことから、糸姫自身も豊臣秀吉と深いかかわりがありました。
まず豊臣秀吉の養女となり、そのあと豊臣秀吉が重用していた「黒田孝高」(くろだよしたか:別名:黒田官兵衛[くろだかんべえ])の息子「黒田長政」(くろだながまさ)のもとへ、正室として嫁ぎます。
当時、黒田孝高は糸姫の父・蜂須賀正勝と共に家臣として重要な存在。そのため、この結婚には黒田家と蜂須賀家の繋がりをより強固にしたいという豊臣秀吉の思惑があったと考えられているのです。
黒田長政と糸姫の間には娘の「菊」(きく:のちに黒田家の家臣・井上庸名[いのうえもちな]へ嫁ぐ)が誕生。しかし、1598年(慶長3年)に2人は離縁。その理由は、「徳川家康」(とくがわいえやす)と同盟を結んだ黒田長政に、徳川家康の養女「栄姫」(えいひめ)との縁談が持ち上がったため。また、糸姫に男児が生まれなかったためという説もあります。
離縁させられた糸姫は、そののち自身の兄「蜂須賀家政」(はちすかいえまさ)が領主を務める阿波国(あわのくに:現在の徳島県)へ行き、1645年(正保2年)に亡くなりました。
糸姫を一方的に離縁した黒田長政は、そののち「関ヶ原の戦い」(せきがはらのたたかい)で大きな成果を挙げますが、この糸姫との離縁により蜂須賀家との間に因縁が生じてしまったのです。この両家の険悪な関係は、江戸時代中期頃まで続いたと言われています。