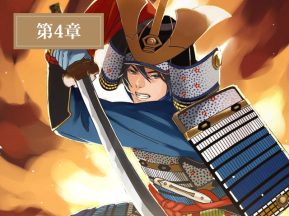ことが起きたのはつい先日のことだ。山名満幸は領地である伯耆の国(現在の鳥取県)にある後円融上皇(ごえんゆうじょうこう)の御料を力尽くで接収。無論、幕府も即時返却するよう御教書(命令書)を発給したが、山名満幸はこれを無視した。
足利義満は、出雲と伯耆の守護職を召し上げ、都から山名満幸一党を追放した。この処置を逆恨みした山名満幸は、ますます意固地になっているようだ。
「馬鹿なことをしたものだ。ようやく天下が治まってきたというのに」
足利義満は不機嫌そうな顔でため息を吐く。
幕府が成立して半世紀が過ぎた現在でも、幕府の不安定は続いている。
そもそも初代将軍・足利尊氏(あしかがたかうじ)以来、将軍の立場は有力大名の連合の上に立つもので、基盤そのものが脆弱だったこともある。
そのときの有力守護といかに手を組むかで立場も影響力も変わるうえに、肉親や家臣がいがみ合うケースも多く、観応の擾乱(かんのうのじょうらん)が起きたり、離反した大名が南朝に降ったり、たびたび起きる政変で管領が代わるなど、不測の事態が発生する。時には初代尊氏が自ら南朝に降ったこともあるくらいだ。
「祖父尊氏が幕府を開いてから55年、余が将軍職を引き継いだあともなかなか太平の世が訪れぬ。そればかりか身内であるはずの幕府内部でも、争乱の種は至るところで燻るばかりだ。これは人の欲深さが原因と言えようが、同時にそれにつけ込む『闇の者』に要因があると思う。余はこれを何としても排除したい」
「人の心の内は目に見えませぬが、『闇の者』はそうでもありませぬからな」
表情を変えず口にする波木に、細川頼之が言った。
「ゆえに無理を承知で頼みたい。山名を探ってほしい。そして世に争乱を招く輩を討つべく手を貸してもらいたいのだ」
「なるほど……」
波木は天を向いて目を瞑り、しばしの間、黙考した。南條忠信は不思議だった。自分に『闇の者』と戦う術を伝授したのは波木なのに、何を迷う必要があるのだろう。
「名誉のお役目とは存じますが、ご辞退申し上げる」
「やはり、難しいか……お主なら山名も聞く耳を持つと思うのだが」
波木の返答を予想していたのだろう。足利義満は波木を見ながら嘆息した。
「かつての私であれば、喜んで拝命したでしょう。ですがその頃の私はすでに死んだとされております。ここにいるのは隠遁者の波木某。死人が世に出ては、これも世の争乱の原因になります。代わりにそこに控える南條忠信と朝妻秀頼を勅使に命じるようお願いいたします」
「波木の推挙であれば考えぬではないが、荷が重過ぎはしないか」
「相手が『闇の者』の可能性があるのなら、遣使(けんし)を任に当てるのは当然。両名とも若輩者でありますが、すでに歴戦の遣使(けんし)に引けを取らぬ経験を積んでおります。及ばずながら私が彼らを手助けします」
「補佐であれば引き受けると」
「はい」
波木の返答を聞いて、足利義満は肩をすくめた。
「では、南條忠信に朝妻秀頼。お前達を使者に任じる。将軍の意を汲み役目を果たせ。波木殿には改めて依頼したい。彼らを助けてやってくれ。くれぐれも彼らが先走らぬようにな」
「かしこまりました」
細川頼之の言葉に波木は深く頭を下げる。
「ところで波木殿、無理を承知での相談だが、再び幕府に帰参する気はないか。もちろん河内は引き渡す。兵も十分に用意するゆえ」
「将軍さま直々のお誘い、恐悦至極に存じますが、なにとぞご容赦いただきたい」
「やはりそうか。残念だ」
断られるのを予想していたのか、足利義満に立腹した様子はなかった。そこで波木は居住まいを正すと、今度は自分から口を開いた。
「ところで、このたび都に馳せ参じる道中、南條忠信と朝妻秀頼とともに、これまで見たこともない『闇の者』と遭遇しました」
「なに、お主すら見たこともない『闇の者』だと?」
足利義満と細川頼之は驚愕した。『闇の者』は人間に憑く先入観があるだけに、にわかには信じられぬに違いない。疑念が先立つのだろう。南條忠信が波木の指示で、道中で戦った異形を詳しく話すと、なおさら驚愕の色が濃くなった。
「まさか、そんな化け物がこの世に」
「非礼ながら申し上げます。このような異形が世に現れる事態です。『闇の者』は我らの知らぬ場所で勢力を拡大していると見るべきでしょう。早急に、遣使(けんし)側の人員増強を急ぐ必要があります。将軍と細川頼之殿にはぜひご検討いただきますよう」
波木は足利義満と細川頼之に向かい再度一礼してから席を立つ。南條忠信もそれに倣うと、急いで波木にしたがった。