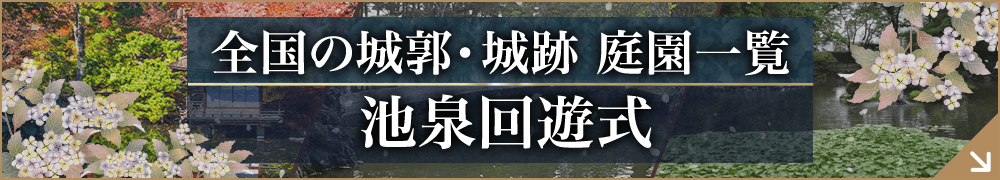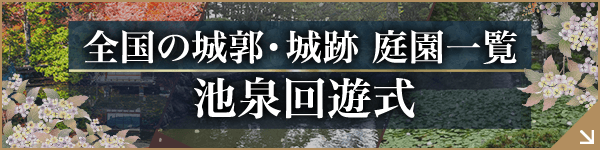平橋
「平橋」(たいらばし)は、橋の上部が平らで、まっすぐな形状をした橋のことです。橋面に傾斜や反りがなく、水平に近い構造のため、通行しやすいのが特徴。歩行者だけではなく、車椅子、高齢者なども安全に渡ることができ、実用性の高い橋として、様々な場面で使用されます。
平橋は、都市部の道路、公園、公共施設など日常生活に密着した場所に数多く設置。橋としての機能を果たしながら、周囲の景観と調和しやすいため、控えめでシンプルなデザインが求められる場所に適しています。

平橋
反橋・太鼓橋
「反橋」(そりはし)は、橋の中央が高く、橋全体がアーチ状に大きく反り上がった橋のことです。橋の形状が太鼓の胴に見えることから、「太鼓橋」(たいこばし)と呼ばれることも。主に神社や日本庭園など神聖で格式のある空間に設けられており、実用性よりも象徴性と景観美を重視しています。
特に神社に設置される太鼓橋は、俗界と神域を隔てる結界的な意味があり、橋を渡ることで、神聖な空間へ入っていくと言う儀式的な役割を担っているのです。

反橋・太鼓橋
八橋
「八橋」(やつはし)は、池や小川などに幅の狭い橋板を数枚、稲妻のようにジグザグに連ねて架ける橋のことです。八橋という名前は、平安時代の歌物語「伊勢物語」に登場する「三河国八橋」(みかわのくにやつはし:現在の愛知県東部)という地名に由来。ここでは、川の流れが8つに分かれ、それぞれ橋が架かっているため、八橋と呼ばれていました。
なお、伊勢物語では、歌人「在原業平」(ありわらのなりひら)が橋のほとりに咲くカキツバタを見て歌を詠む場面が描かれています。これにちなんで、八橋の周辺には、カキツバタが植えられることが多く、訪れる人は、季節の風情を楽しむことができるのです。

八橋