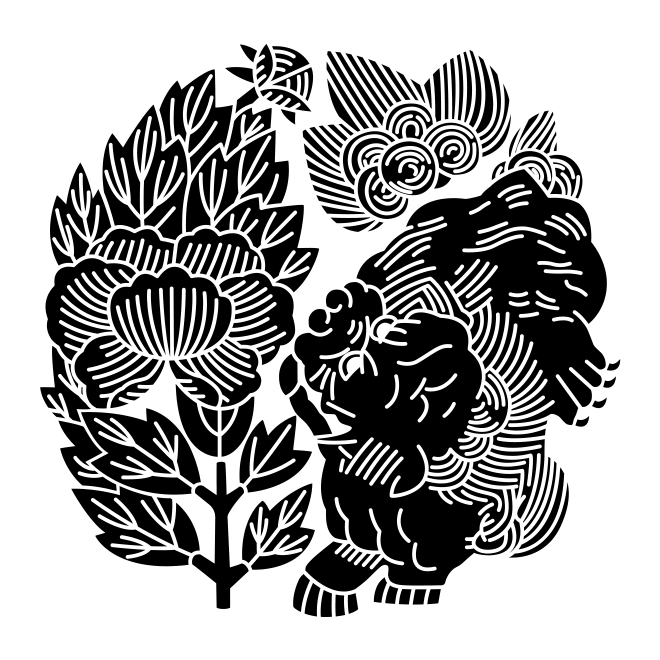
獅子と牡丹が向かい合う「獅子に牡丹」は、取り合わせの良い高貴なものの例えを表す慣用句として用いられています。
獅子は仏教の世界で、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)が乗る動物とされてきました。また、古代インドの商人「維摩居士」(ゆいまこじ)をモチーフにした鎌倉時代の彫刻に、獅子と牡丹が見られます。維摩居士の経典「維摩経」(ゆいまきょう)は「聖徳太子」によって日本で解説された仏典のひとつ。このことから、獅子は悟りを開いた者が乗る動物として扱われたと見られ、仏教との関係性が見出せます。
家紋として使われ始めた経緯は明らかになっていませんが、「応仁の乱」(おうにんのらん)で東軍に付いた諸将の記録「見聞諸家紋」(けんもんしょかもん)では、獅子に牡丹紋は、武具に描かれていたと見られる多田家や諏訪家の家紋として記録。仏教では、獅子が牡丹を食べることで毒虫(仏の敵)から身を守ると考えられていたことから、魔除けの意味と、自身の正義を守り抜こうとする意味合いがあったと推測できます。
獅子に牡丹が高貴なことを表す語に用いられるのは、こうした思想的背景があるからです。獅子に牡丹紋は、摂津源氏(せっつげんじ:大阪府北部周辺を根拠地とした源氏一族)の中川家や多田家が使用。摂津源氏では、のちに獅子を省略した牡丹のみの家紋を用いた家も多くありました。
家紋データ
| 家紋の種類 |
|
|---|---|
| 代表的な家 |
|
























