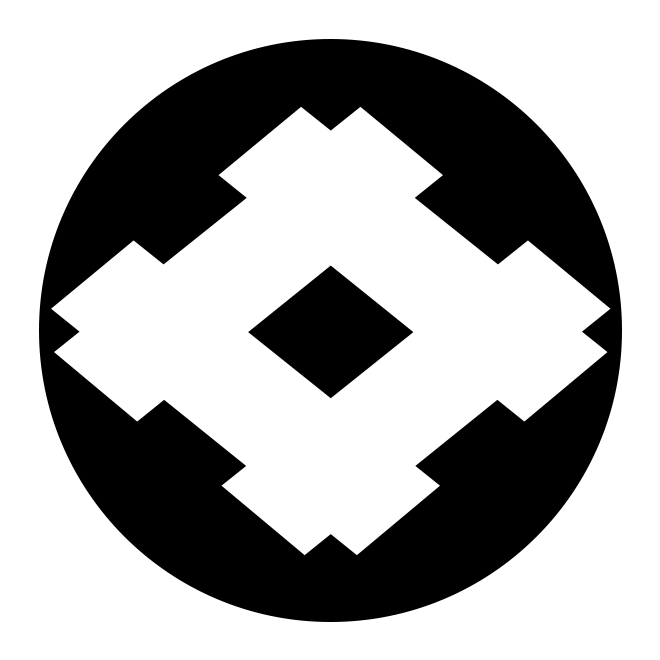
井桁と井筒は、どちらも井戸の囲いを意味します。井戸は、生活を支える貴重な水源として大切にされてきたことから、家紋にも採用されました。井戸の一部としては、井の字型の木組が「井桁」、円形のものが「井筒」です。
家紋では、菱形のものを井桁、正方形(井の字)のものを井筒と呼びます。井伊家のように、名字の一部に「井」の字を含む多くの家が、家紋として使用していました。井桁(井筒)紋は単独で用いられるだけでなく、他の家紋と組み合わせられることが少なくありません。
井伊家は、2つの家紋を使い分けています。井桁(井筒)は替紋(かえもん:非公式の家紋。旗印などに使用される)で、公式の家紋である定紋(じょうもん)には、橘(たちばな)を使っていました。井伊家には井桁(井筒)紋の由来にまつわる2つの説があります。
ひとつは、井伊家の初代「井伊共保」(いいともやす)が、子どものときに橘が生えている井戸のそばに捨てられていたという説です。この説は、中国の「橘井選考」という逸話の転用とみられ、史実である可能性が低いと考えられています。もうひとつは、井伊と呼ばれる地域を本拠地としたためという説です。武家の家紋を収集した記録「見聞諸家紋」(けんもんしょかもん)に井の字の紋が掲載されていたため、有力な説だと考えられています。
家紋データ
| 家紋の種類 |
|
|---|---|
| 代表的な家 |
|
| 代表的な武将 |
























