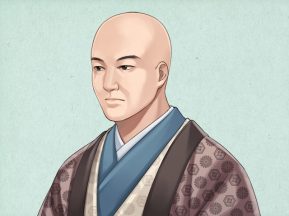小姫
「小姫」(おひめ)は、「織田信長」(おだのぶなが)の次男「織田信雄」(おだのぶかつ)の長女です。1585年(天正13年)頃に誕生。
生後間もなく「豊臣秀吉」(とよとみひでよし)の養女となり、5歳になると、のちに江戸幕府2代将軍となる「徳川秀忠」(とくがわひでただ)と婚約。この結婚は、豊臣家と徳川家の縁組という重要な意味が込められており、「小田原征伐」(おだわらせいばつ)を目前にした豊臣秀吉による政略結婚と考えられています。
しかし、実際には小姫は徳川秀忠と結婚せず、1591年(天正19年)に病死。正確な生年が分かっていないことから享年も定かではなく、亡くなったのは6~7歳頃だったと考えられています。
幼くして亡くなったことから、小姫に関する史実はあまり多くありません。しかし、亡くなった際の法要は、豊臣秀吉が母のために建立した「天瑞寺」(てんずいじ:京都府京都市)で行われたという説があります。この天瑞寺はかつて「大徳寺」(だいとくじ:京都府京都市)という寺院内に建てられた寺でしたが、大徳寺が廃寺となり現在は存在していません。
一方、1812年(文化9年)に編纂された「寛政重修諸家譜」(かんせいちょうしゅうしょかふ:江戸幕府が編纂した大名・旗本の家系図集)では、小姫は織田姓へ戻って1641年(寛永18年)まで生きたとの記述もあるなど、その生涯についてはいまだに謎が多いのです。