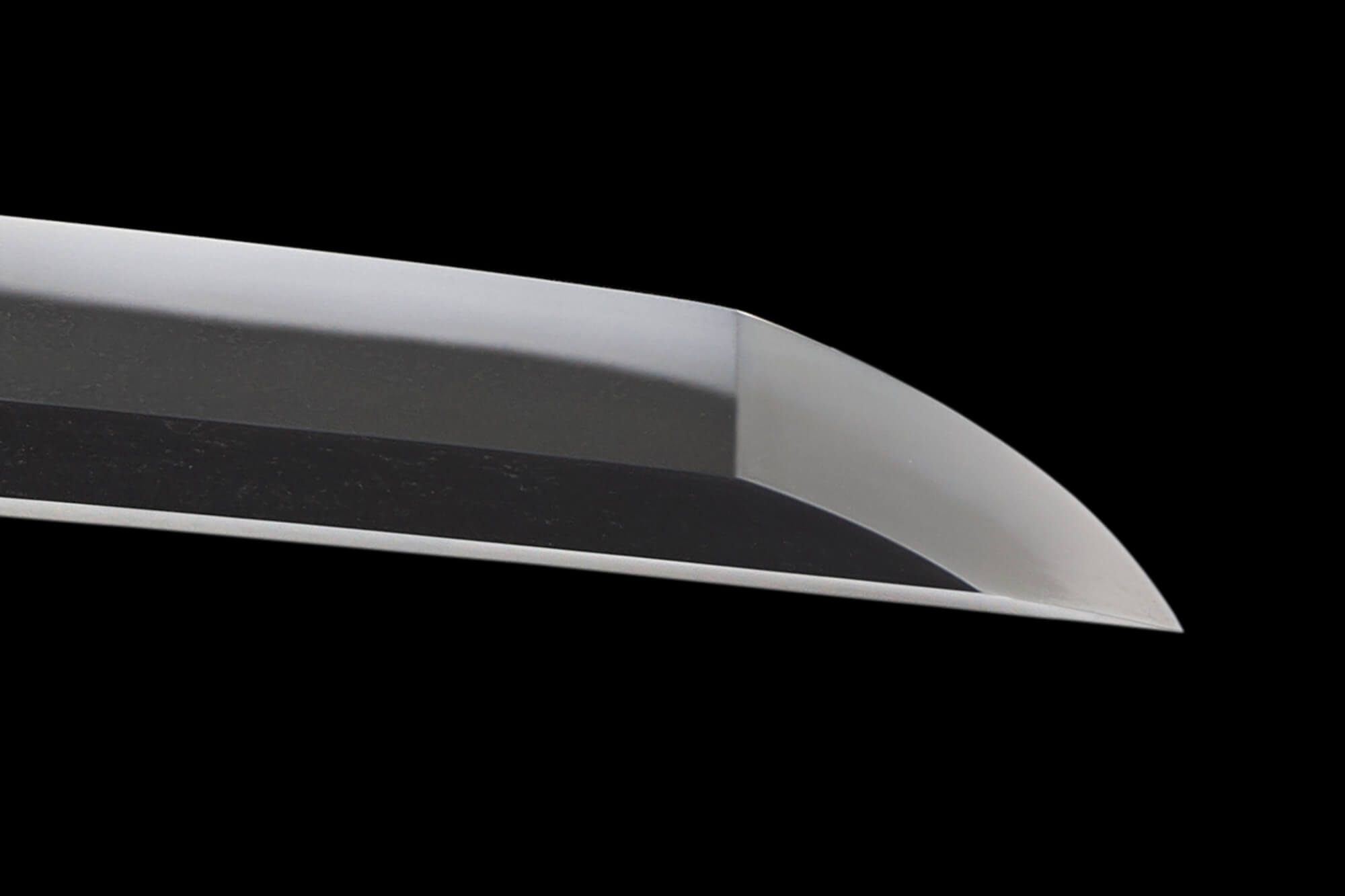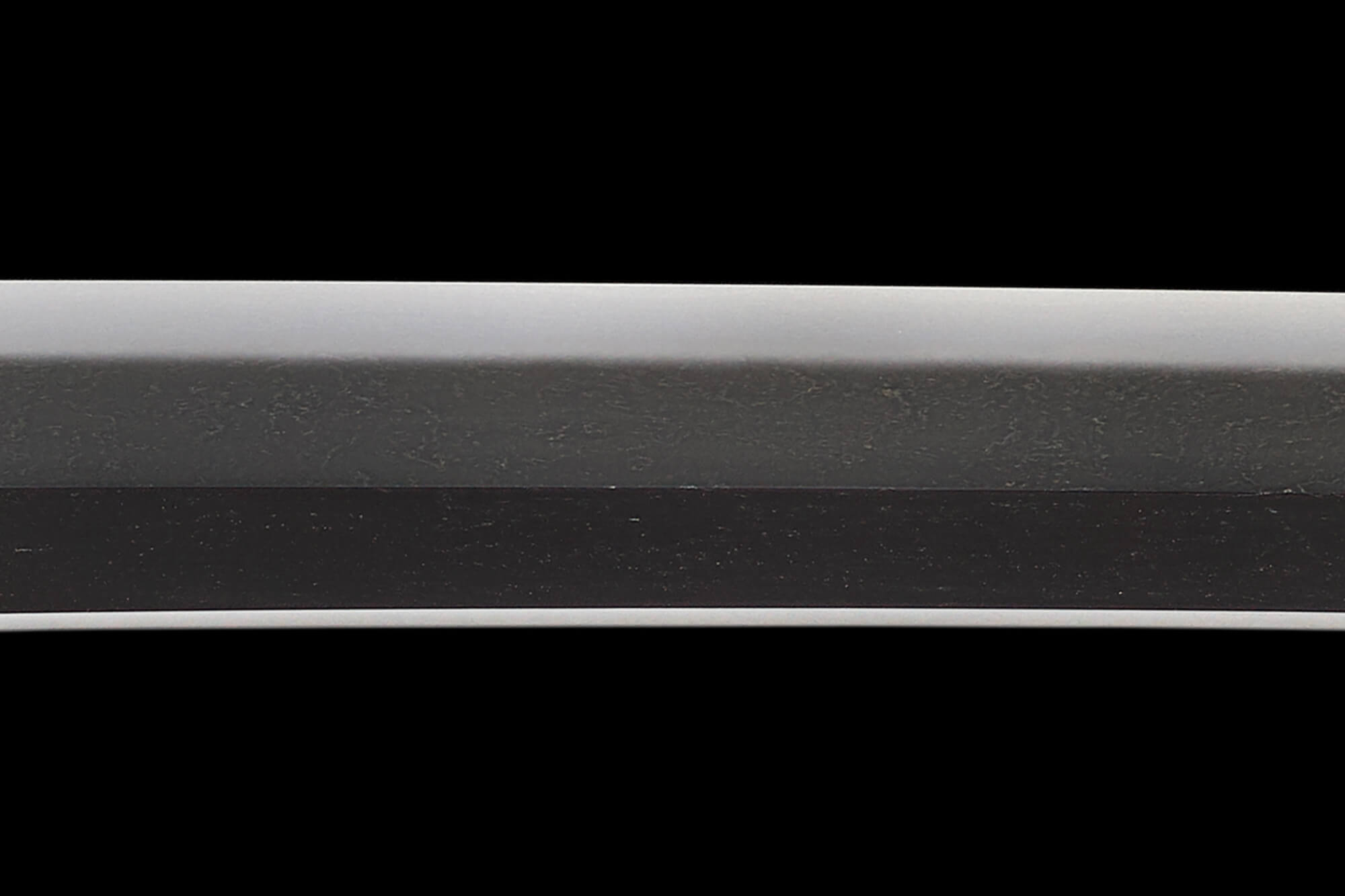土佐藩(現在の高知県高知市)を領していた山内家には、多数の古名刀がありましたが、この国広は、第3代藩主「山内忠豊」(やまうちただとよ)の愛刀の1振りと伝わっています。
忠豊は、1609年(慶長14年)、第2代藩主「忠義」(ただよし)の長男として生まれ、1656年(明暦2年)に家督を継いで藩主となりました。そして、忠義が重用した奉行職「野中兼山」(のなかけんざん)をそのまま引継ぎ、伊予宇和島藩(現在の愛媛県宇和島市)との国境争いに決着を付けるなどしたのです。
しかし、兼山の強硬な政策に領民からの不満が募ったため、叔父で伊予松山藩(現在の愛媛県松山市)藩主「松平定行」(まつだいらさだゆき)の同意を得て兼山を罷免。
それから藩政改革が行なわれ、兼山の施政期に定められた諸制度が緩和されました。土佐藩史上、最も画期的だったと言えるこの政変は、「寛文改替」(かんぶんかいたい)と呼ばれ、これによってその後の藩経済が安定成長期に移行したのです。
国広は、日向国古屋(ひゅうがのくにふるや:現在の宮崎県東諸県郡綾町)の出身で、壮年の頃まで同国・飫肥藩(おびはん:現在の宮崎県日南市)の領主・伊東家(いとうけ)に仕えていました。しかし、1577年(天正5年)、薩摩藩(現在の鹿児島県鹿児島市)藩主の島津氏によって同家が没落すると、山伏となって父・国昌(くにまさ)より鍛刀の術を学びます。
そして、日向国を出て、一時は「上杉謙信」(うえすぎけんしん)に仕えただけでなく、征韓の軍にも従い、釜山でも鍛刀していたと言われているのです。
1591年(天正19年)頃には京都にも住み、「埋忠明寿」(うめただみょうじゅ)の門人となりました。その後は自身の門人の養成にも尽力し、大教育家であった国広の門下からは、幾人もの新刀鍛冶の名工を輩出。国広は、まさに「新刀の祖」と評されるのにふさわしい名工だと言えます。
本刀の指裏に切られている年紀銘「慶長十五年四月四日」は、同作中他の刀にも見られますが、四月四日がどのような意味を示しているかは不明です。