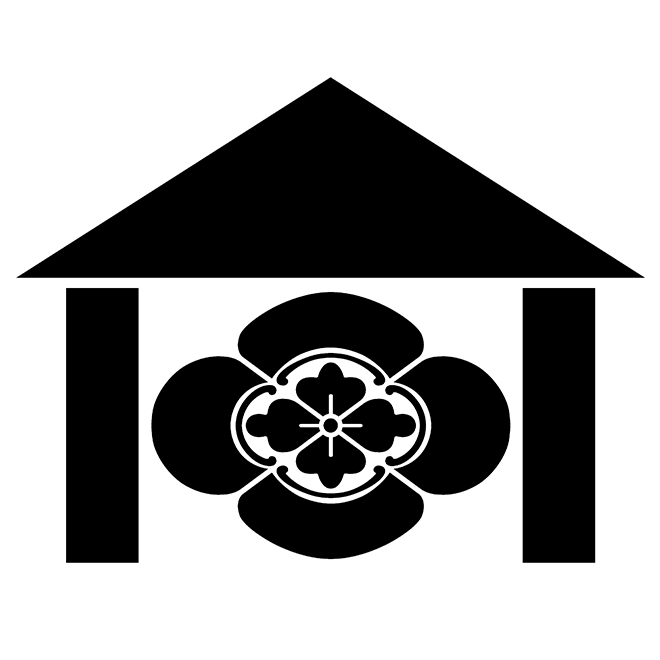
庵とは、草木で作られた粗末な仮小屋を指し、僧侶や世捨て人が住む趣のある住居という意味も含む言葉です。庵紋は単独で使用されることが少なく、他の家紋と組み合わせて使用されることが多い模様。中世と近世では形状が異なり、中世の室町時代まで、Uの字を逆さにして左右を払い、頂部に十字が付いた釣鐘のような形状が主流でした。
近世の江戸時代以降、家紋に庵紋を組み合わせる家が増え、積み木型が庵紋の代表的な形状となりました。積み木型で有名な庵紋は、庵木瓜(いおりもっこう)です。木瓜(もこう)は、開いた花のように見える図柄。ウリを輪切りにした形、鳥の巣が卵を包んでいる様子を表す形という説があります。帽額(もこう:御簾やすだれの掛け際を飾る横長の織物)に多く用いられた柄のため、当て名が付けられました。
庵木瓜は、藤原南家(ふじわらなんけ:藤原不比等[ふじわらのふひと]の長男である藤原武智麻呂[ふじわらのむちまろ]を祖とする家系)の流れを汲む伊東姓が多い関東地方や、工藤姓の多い東北地方で見られます。庵木瓜は、「曽我物語」に登場する「工藤祐経」(くどうすけつね)の家紋でもありますが、物語の舞台は鎌倉時代であり、江戸以前に積み木型の庵紋使用の文献がないことから、江戸時代以降に家紋が変更された可能性が高いです。
家紋データ
| 家紋の種類 |
|
|---|---|
| 代表的な家 |
|
| 代表的な武将 |
|
























