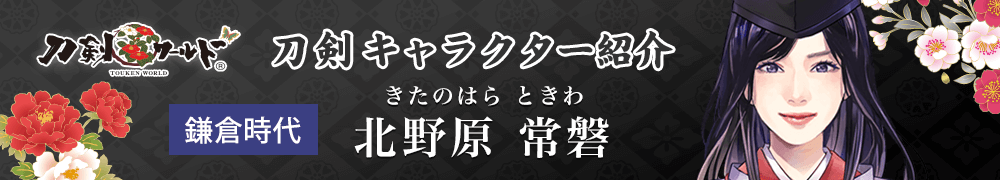「して定房卿、お話はもっともなれど、貴殿が招いたこの窮地、いかに脱するおつもりか。もちろん何かしら手立てはあるのでしょうな」
きつく問い詰めようとする千種忠顕に、吉田定房は頭を振って応えた。
「遺憾ながら、事ここに及んでは、無事に済ませる手立てなどありはせぬ」
「なんですと、ではいかにこの窮地を脱せよと言うのか」
「貴殿らは帝を奉じて裏門より脱出するのだ。すでに近習達に命じ、裏門に輿を用意させておる。いまのうちならば六波羅も兵を回しておるまい」
定房は帝へと振り返ると、頭を深く下げて言上した。
「恐れながら主上、時は臣が稼ぎますゆえ、同道される皆様方と一刻も早く落ちられますよう」
「落ちて、どこへ向かえと言うのだ」
後醍醐天皇は低い声で眼を細めた。吉田定房の真意を探っているようだ。
「まずは比叡山へ。途中、大塔宮親王が合流されます。そののちは殿下とともに、南都に赴かれませ」
南都とは、奈良の平城京を指す言葉だ。吉田定房は後醍醐天皇が御所から逃れたあとの行く先として、受け入れを東大寺と金胎寺に要請していた。
「なるほど。手立てはそれしかない訳じゃな」
「定房卿、帝の矜持を示すため、急ぎ綸旨を発して心ある武士を呼び寄せてはいかがか」
「さよう。六波羅に一太刀でも浴びせぬまま、御所を離れるというのは末代までの恥ぞ」
公家達は御所を離れたくないようだ。吉田定房はそんな彼らを冷たい顔で突き放した。
「間に合いませぬな」
「何故そう言いきれる」
「綸旨を発したところで、誰が明朝の襲撃に間に合いましょう。御所で幕府に捕まるより、他の地で志を同じくする者を募るべきと愚考いたしまする」
「確かに、定房の申すほうが朕らしい」
後醍醐天皇は納得したようだ。一時は京を離れたとしても、また取り返せば済む話だ。還御(かんぎょ:天皇が出先から帰ること)がいかなる形であったとしても、最後に勝利するまで後醍醐天皇が倒幕を諦めることはないだろう。
「ところで、定房はどうするのじゃ。朕とともに都より落ちるか」
「臣はこの場に残ります」
「なぜじゃ」
「六波羅の先触れをこの場にとどめ、わずかでも時を稼ぎます。臣ができる償いはそれくらいにございます。仮に臣とともにこの場に残る方がおられるならば、幕府に恭順するものとして処罰を受けぬよう取り計らいます」
「そうか……」
結局、すべての公家達が帝を奉じて御所を出る運びとなった。千種忠顕や阿野廉子をはじめとする数人の側近は、部屋を出る際、吉田定房に心ない声を浴びせていく。
やがて広い部屋に後醍醐天皇と吉田定房、北野原常磐の3人が残った。後醍醐天皇は記憶に焼き付けるように御所の内部を見回すと、最後に吉田定房の肩を軽く叩いた。
「定房、朕は必ず京に生きて戻るぞ。例え草を噛み、泥水を啜っても、必ずこの場に帰ってこよう」
「この定房、主上のお帰りをいつまでもお待ちしております」
そこで吉田定房は、後醍醐天皇に『闇の者』の脅威を伝えた。人の世にあって人の理の通じぬ者だけに、人を体現する後醍醐天皇は『闇の者』にとって排除する対象でしかない。吉田定房はかねてから遣使(けんし)とよしみを通じており、後醍醐天皇の側近でいち早く『闇の者』を危険な存在と認識していた。後醍醐天皇はそれを聞かされていたが、いまいち実感が伴わないようだ。
「主上、北野原常磐の側から決して離れませぬよう」
吉田定房が、後醍醐天皇の目を見据えて言った。
「この者は女性ではありますが、『闇の者』を察知する能力を持ちますゆえ、必ずお役に立ちましょう」
「分かった。そちの忠告に従おう。常磐は此度の一件が落ち着くまで、我が手元に置くとする」
「お聞き届けいただき、ありがとうございまする」
「ときに定房よ、ひとつ腑に落ちぬ件があるのだが」
後醍醐天皇がいぶかしげな顔で口にした。
「なぜ『闇の者』は朕の命を奪おうとするのか」
「簡単でございます。主上はのちの世に偉大な功績を残す御方。それは日の本に災いをもたらさんとする彼らにとって、大きな不都合となるのでしょう。いずれ大きな力を持つ前に排除しようとするのは、彼らの理屈からすると至極当然かと」
「そうか、朕は後世に偉大な業績を残すのか」
滅多に笑わない後醍醐天皇と吉田定房の顔に、やわらかな笑みが浮いた。
「なれば、なおさら此度のごとき些事で命を落とす訳にはいかんのう」
「お急ぎを。とにかく大塔宮親王と合流するのです」
促す吉田定房に帝が告げた。
「定房よ、死ぬでないぞ。朕が思い描く政治には定房が必要じゃ。例え朕の意志に反そうとも、誠の忠義を尽くす男がな」
1度行動を起こした後醍醐天皇は大胆だった。素早く直垂(ひたたれ)を脱ぎ捨てると、近習達に女装の手はずを命じたのだ。
「朕はあらゆる手段を用いてこの窮地を脱する。まさか異論はあるまいな」
反対する公家達を威圧すると、帝は輿に乗り御所からの進発を指示した。公家達も重い足取りであとに続く。これから長く続く道のりを思えば、公家達が暗澹たる気分になるのも分かる。
だが、まさか裏門から出た途端、六波羅の軍勢が待ち受けているとは思わなかった――。